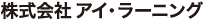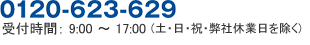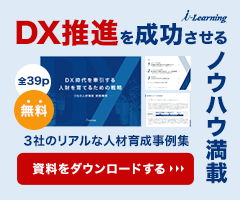【メタエンジニアの戯言】可視化された情報共有と精神衛生
2024.11.06松林弘治の連載コラム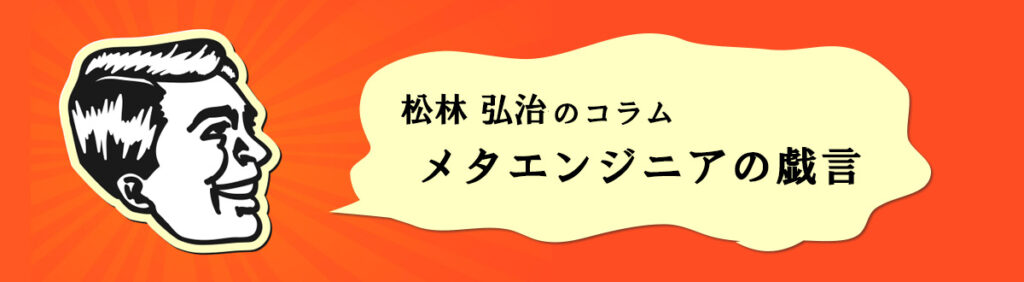
これを書いている10月は、とあるプロジェクトで10日連続オンライン打ち合わせ(といっても2名でのブレストや情報整理、制作などでしたが)などがあり、ドタバタとした1ヶ月でした。
オンライン・オフラインを問わず、複数人での共同アイデア出しや整理、タイムライン(スケジュール)やタスク進捗の管理、成果物の共有や共同編集、などを進めていくためには、今となっては各種オンラインツール・サービスの活用が欠かせません。
Wiki 的なナレッジ共有ツール、カンバン方式のツール、チケット単位でのプロジェクト管理、ガントチャートでのスケジュール管理など、さまざまなツールやサービスが存在しており、使い勝手や勘所もそれぞれで、混乱してしまいそうですね。
わたし自身は、個人的に常用しているものは数種類 に限られますが、共同開発の現場では現在に至るまで例えば Redmine / Jira / Backlog / Miro / Notion / Jooto / GitHub Issues / Wunderlist / Trello など、数多くのツールを使用してきました。しかし一方で、組織や企業によっては、特定の企業のプロダクト以外を使ってはいけないという縛りがあるところも多いでしょうから、あれもこれも試すことができない、という立場の方もいらっしゃるでしょう。
に限られますが、共同開発の現場では現在に至るまで例えば Redmine / Jira / Backlog / Miro / Notion / Jooto / GitHub Issues / Wunderlist / Trello など、数多くのツールを使用してきました。しかし一方で、組織や企業によっては、特定の企業のプロダクト以外を使ってはいけないという縛りがあるところも多いでしょうから、あれもこれも試すことができない、という立場の方もいらっしゃるでしょう。
いずれにせよ、ツールは手段であって目的ではありません。重要なのは「ナレッジの共有」「1タスクの範囲の明確化」「主たる担当者の明確化」「進捗の見える化(残課題と依存関係の可視化)」、そしてこれらが全プロジェクトメンバに共有されている状態を作ること、でしょう。
———
で、今月の毎日オンラインミーティングの際には Notion を使ったのですが、相手の方が Notion を日常的に使用されていない方であった(しかし是非使ってみたいと意欲的であった)ため、最初は単なるオンラインドキュメント共同編集ツールとしてメモ書きから始め、アイデア出しや議論が進むにつれて、いろんな機能を試してみながら、コンテンツの体裁や構造を進化させていきました。
とはいえ、特定のツールの使いこなし方の習得が主目的ではありませんので、あまり深掘りせず、ブレストの進行を阻害しない範囲内でツールのティンカリングを並行していきました。
結果、アイデアのタネとなるものを単位にして個別ページとし、それぞれにタグやステータスをつけることでデータベース化した状態で管理する、というシンプルな形態で一旦落ち着きました。
その上で、このアイデアと別のアイデアは連続性があるよね、とか、同じカテゴリにまとめられるよね、といった議論が進むにつれ、データベース化された共有メモ・ナレッジはどんどん変化し続けています。
また、相手が新しい内容を追加したり、コメントをつけたことが通知されるため、実際にオンラインミーティングを行なっていない「非同期の」時間帯でも、共同で作業をしている感覚を持ちやすくなります。
———
このように、共同作業者と「可視化された情報共有」ができる状態を整備することは、作業内容の明確化につなげやすいですし、なにより精神衛生上非常に好ましいというか(笑)風通しの良さにも貢献していると感じています。
しかし、それがかなわない現場もあります。社内コンプライアンスのため、社外メンバによるツールの使用にさまざまな制限がかかっていたり、SharePoint Online 上の Word ドキュメントをビデオ会議中に画面共有するのがせいぜいだったり、伝言ゲームが発生しやすい運用になっていたり、さまざまです。
責任者や意思決定層に直接話をする機会がある場合は、風穴をあけられることもありますが、当然全てのプロジェクトや現場がそうではないため、従事されている外部開発者の方々はなかば諦め気味というか、モチベーションが下がった状態で粛々と遂行しているなんて場面を目にすることもあります。
残念ながら、これらは単純に技術レイヤーだけの話ではないことがほとんどでしょうから、簡単にどうにかなるものではありませんが、プロジェクトの効率的・効果的な遂行のためにも、全てのレイヤーの方々が気持ちよく仕事に邁進できる、そんな環境作りをこれからも目指していきたい、と強く思いました。

松林 弘治 / リズマニング代表
大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期過程修了、博士後期課程中退。龍谷大学理工学部助手、レッドハット、ヴァインカーブを経て2014年12月より現職。コンサルティング、カスタムシステムの開発・構築、オープンソースに関する研究開発、書籍・原稿の執筆などを行う。Vine Linuxの開発団体Project Vine 副代表(2001年〜)。写真アプリ「インスタグラム」の日本語化に貢献。鮮文大学グローバルソフトウェア学科客員教授、株式会社アーテックの社外技術顧問を歴任。デジタルハリウッド大学院講義のゲスト講師も務める。著書に「子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい」(KADOKAWA)、「プログラミングは最強のビジネススキルである」(KADOKAWA)、「シン・デジタル教育」(かんき出版)など多数。


 【メタエンジニアの戯言】「個別指導」最強説
【メタエンジニアの戯言】「個別指導」最強説 【メタエンジニアの戯言】コスパとタイパは今のためならず
【メタエンジニアの戯言】コスパとタイパは今のためならず 【メタエンジニアの戯言】教育(共育)のKPIとジレンマ
【メタエンジニアの戯言】教育(共育)のKPIとジレンマ 【メタエンジニアの戯言】情報技術による「記憶の外部化」
【メタエンジニアの戯言】情報技術による「記憶の外部化」 【メタエンジニアの戯言】生成AIと外注の共通点
【メタエンジニアの戯言】生成AIと外注の共通点 【メタエンジニアの戯言】「名もなき家事」と論理的思考力
【メタエンジニアの戯言】「名もなき家事」と論理的思考力