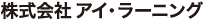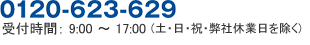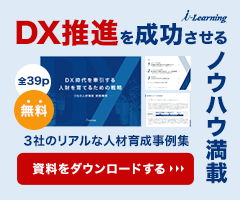【メタエンジニアの戯言】「質より量」はもう流行らない?!
2025.02.05松林弘治の連載コラム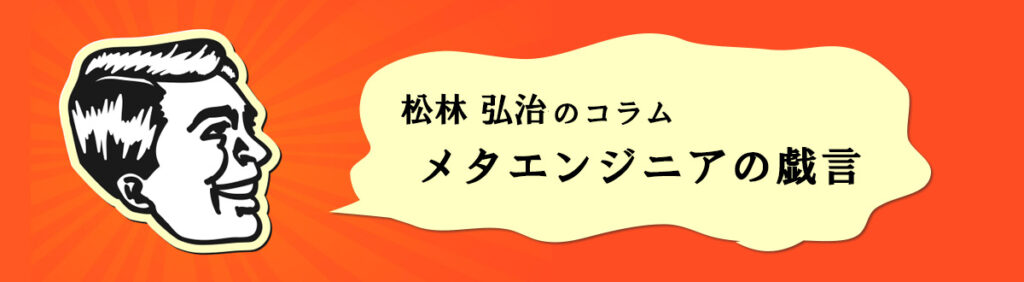
一向に上級者になれないままの私が飽きもせず取り組み続けているテニス、体が衰える前にどうしても上達したいという思いが昂じて、ここ2ヶ月くらい、毎日のように地味な壁打ち練習を早朝の公園でやっています。
当初は「毎日30分のワークアウトができるだけで御の字」 程度の気持ちでしたが、継続は力なりというか、「自分にとって今何が課題か」「そのためにはどこを工夫する必要があるか」「どんな練習がいま自分に必要か」などに関する気づきが増え始めました。その結果、2ヶ月前より圧倒的にミスが減り、強いトップスピンとスライスのボールが楽に打てるようになってきています。とはいっても、あくまで「自己ベスト更新」であり、客観的なレベルはまだ低いままでしょうが…
程度の気持ちでしたが、継続は力なりというか、「自分にとって今何が課題か」「そのためにはどこを工夫する必要があるか」「どんな練習がいま自分に必要か」などに関する気づきが増え始めました。その結果、2ヶ月前より圧倒的にミスが減り、強いトップスピンとスライスのボールが楽に打てるようになってきています。とはいっても、あくまで「自己ベスト更新」であり、客観的なレベルはまだ低いままでしょうが…
この不肖のテニス練習の話を一般化するのはさておき(笑)、ビジネスの世界、エンジニアの世界、その他あらゆるところで「質は大事だが、その前にまず圧倒的に量が必要」という言説をよく目にします。「量質転化の法則」という言い回しもよく知られています。すなわち、「無心でむやみに数をこなす」のは無意味である一方、「意識的に考えながら数をこなす」ことで、ある閾値を超えると急に理解が深まったり上達したりする、といった主張です。
このように、「技術の上達」や「深い理解」を身につけるために、熱心に取り組まれている方も少なくないでしょう。我々エンジニアの世界では、書籍を読んだりwebで情報を探したりしながら、どんどん試行錯誤して実践を積み重ねていくわけですが、少し気になることもあります。
——
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、2011年に「Googleが記憶に与える影響」という論文が発表されました。オンライン検索を頻繁に行う人は、オフラインで調べ物をする人に比べて、調べた情報を記憶・保持していない、という研究でした。
この効果には、のちに「デジタル健忘症」という呼び名が付けられましたが、人間の頭脳に全ての情報を記憶しておくより、情報を外部化する、つまり「あの人に聞けば分かる」「図書館のあの本を見れば書いてある」「この検索キーワードを使えば目的の情報をすぐに探し出せる」と、リンクやヒントだけを記憶しておくことで、「知識の外部化」により人間の負荷を下げる、ということです。
ここまでは、人間の記憶保持能力が低下するかもしれないが、あくまで「記憶領域の拡大」であり、記憶の負荷が軽減することで思考効率や最終成果の品質をあげられる可能性がある、つまり、依然として思考そのものの主体は人間であることは間違いありません。
——
しかし、近年の各種人工知能ツールの登場および劇的な進化により、人間の負荷軽減は「思考」へも向けられている、と言っていいでしょう。
2025年1月に発表された 「社会におけるAIツール: 認知的オフロードと批判的思考の未来への影響」という論文では、666名の被験者に対して行ったアンケートやインタビューを分析した結果、「AIツールの使用頻度と、クリティカルシンキング力に強い負の相関がある」、すなわちAIツールを使えば使うほど、批判的思考力が落ちてしまう懸念があるのでは、という仮説を導いています。
「社会におけるAIツール: 認知的オフロードと批判的思考の未来への影響」という論文では、666名の被験者に対して行ったアンケートやインタビューを分析した結果、「AIツールの使用頻度と、クリティカルシンキング力に強い負の相関がある」、すなわちAIツールを使えば使うほど、批判的思考力が落ちてしまう懸念があるのでは、という仮説を導いています。
人間は誰しも楽をしたい生き物と言えます。そして、楽をするためならどんな努力も厭わない「ハッカー」気質の人であれば、そんなAIツールをいかに活用して自分のパフォーマンスを最大化・拡張するか、それこそ批判的思考力を総動員して取り組むでしょう。
しかし、世の中の全ての人がハッカー気質というわけではありません。組織全体として、社会全体として、中長期の負の影響があるかもしれない、そんな懸念を持つのも不思議ではないでしょう。
冒頭で「質より量」と書きましたが、AIツールを最大限活用することで、量を減らしても質をあげることができる可能性が大いにあります。しかし「それは本当に正しいのか?」「これは質が本当に向上したことになっているのか?」といった思考までやらなくなりAIツール任せになってしまうのも考えものです。
——
だからといって、AIツールを頭ごなしに批判したり、使用を制限すべきと考えたりしているわけではありません。批判的思考力を低下させず、かつ人間の認知負荷を軽減して、さらにパフォーマンスをあげるために工夫する、そういった意識や心構え、取り組みを浸透させることがますます重要になってくるのではないか、そのように改めて考えている次第です。

松林 弘治 / リズマニング代表
大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期過程修了、博士後期課程中退。龍谷大学理工学部助手、レッドハット、ヴァインカーブを経て2014年12月より現職。コンサルティング、カスタムシステムの開発・構築、オープンソースに関する研究開発、書籍・原稿の執筆などを行う。Vine Linuxの開発団体Project Vine 副代表(2001年〜)。写真アプリ「インスタグラム」の日本語化に貢献。鮮文大学グローバルソフトウェア学科客員教授、株式会社アーテックの社外技術顧問を歴任。デジタルハリウッド大学院講義のゲスト講師も務める。著書に「子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい」(KADOKAWA)、「プログラミングは最強のビジネススキルである」(KADOKAWA)、「シン・デジタル教育」(かんき出版)など多数。


 【メタエンジニアの戯言】古くて新しい、小さく大きな DX
【メタエンジニアの戯言】古くて新しい、小さく大きな DX 【メタエンジニアの戯言】人間に近づくほど生まれる不思議な違和感
【メタエンジニアの戯言】人間に近づくほど生まれる不思議な違和感 【メタエンジニアの戯言】人間は「論理」が苦手なのか
【メタエンジニアの戯言】人間は「論理」が苦手なのか 【メタエンジニアの戯言】純粋な心に癒され、そして考えさせられる
【メタエンジニアの戯言】純粋な心に癒され、そして考えさせられる 【メタエンジニアの戯言】出典と文脈確認の重要性
【メタエンジニアの戯言】出典と文脈確認の重要性 【メタエンジニアの戯言】フィードバックは「フィードバック」にあらず?
【メタエンジニアの戯言】フィードバックは「フィードバック」にあらず?