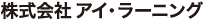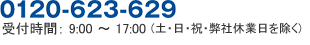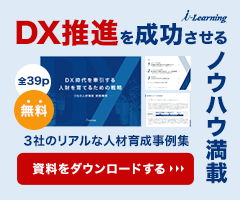【メタエンジニアの戯言】出典と文脈確認の重要性
2024.04.09松林弘治の連載コラム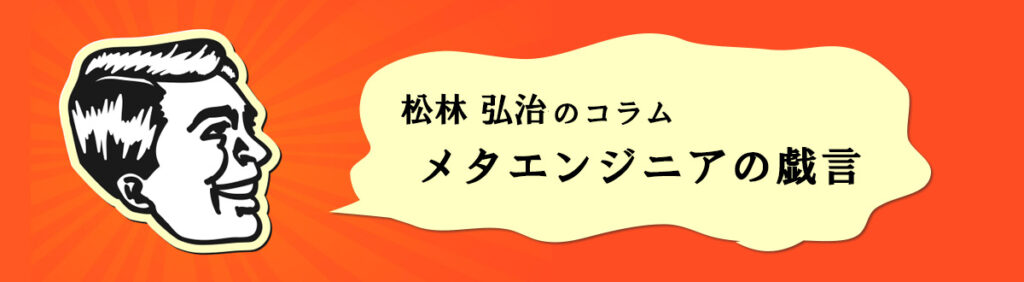 先日、Eテレのなにかの番組の終わりに、次のフレーズが紹介されていました。
先日、Eテレのなにかの番組の終わりに、次のフレーズが紹介されていました。
« L’élève n’est pas un vase qu’on remplit, mais un feu qu’on allume »
「教育とは、花瓶に水を注ぐことではなく、炎を燃え上がらせるものである」といった意味でしょうか。
テレビでは、この格言の出典が、16世紀のフランスの哲学者、ミシェル・ド・モンテーニュ (1533-1592) とされていました。しかし、似たようなフレーズは、過去にいろんなところで目にした気がします。
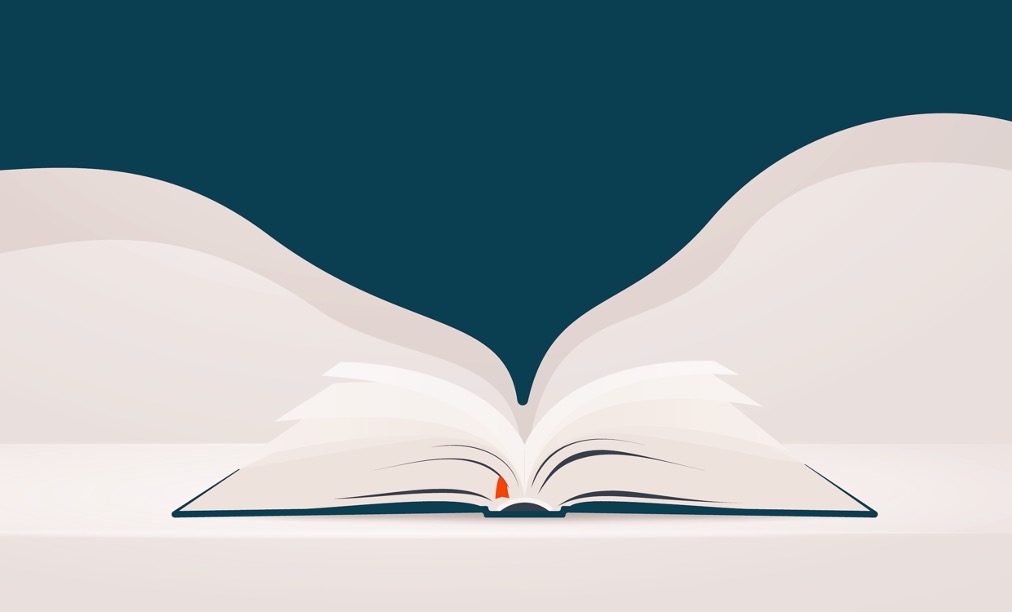 こういう時、正確な出典はなんだろう、つまり、なんという本に書かれていた文言なんだろう、というのが気になってしまいます。そして、調べまくってみたのですが、なんと、自分自身が5年前にあらかた調べ終わっていたことを忘れていた、というオチでした…
こういう時、正確な出典はなんだろう、つまり、なんという本に書かれていた文言なんだろう、というのが気になってしまいます。そして、調べまくってみたのですが、なんと、自分自身が5年前にあらかた調べ終わっていたことを忘れていた、というオチでした…
以下、2019年当時に調べた時のメモを掲載します。
—
「教育とは炎を燃え上がらせるものであり、入れ物を満たすものではない」
という(いかにもそれっぽい)引用句を、David Nunan という教育者に関する web 記事で目にしました。ソクラテスの格言と書いてあります。
で、そんなフレーズ、ソクラテス関連の文庫本で目にした記憶ないよなぁ、そもそも出典はどこなんだろう、と気になって仕方ないので、調べてみました。
英語では
“Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel.”
というのがよく出回ってるフレーズで、Nunan 教授自身は言語教育に関する書籍の中で引用していました。
面白いことに、ソクラテスではなくプルタルコスの引用句とする記事も多いのです。プルタルコスには確かに「子どもの教育について」という著作があるようですが、大学紀要論文に解説があったので読んでみても、そんなフレーズの形跡は見当たりません。むしろ昔気質な教育観満載(笑)の著述に読めます。西洋古典叢書「モラリア」(京都大学学術出版会)に収録されてるらしいので、機会があれば読んでみよう。。。かな(若干消極的)。
とにかく、日本語で検索しても、英語でどう検索しても、出典が一切書かれていないのです。
楽しいので更に調べていくと、今回も、よくお世話になっている格言由来探求サイト「Quote Investigator」の記事にたどりついてしまいました。イェイツ由来説も出回っているんだとか、知りませんでした。
で、結局はこれらの引用の大元をたどると、やはりプルタルコスにいきつくらしく、「On Listening to Lectures (聴くことについて)」に書かれている次のフレーズから変形されたのではないか、と。
“For the mind does not require filling like a bottle, but rather, like wood, it only requires kindling to create in it an impulse to think independently and an ardent desire for the truth.”
このサイトがいつも面白いのは、現在出回っている出自が怪しい格言について、その怪しい出自を丹念にトレースしてくれていることです。今回の場合、炎のメタファー自体はプラトンの第七書簡「シュラクサイのディオン」に現れているそうです。
そして、1892年に Benjamin Jowett (ジョウェット) 氏が「プラトン対話編」を英訳出版する際に Jowett 氏が序文に書いた
“Education is represented by him, not as the filling of a vessel, but as the turning the eye of the soul towards the light.”
の前半部分と、第七書簡の炎のメタファーがなぜか合体し、更にプラトンとソクラテスとプルタルコスがごっちゃになり(あるいは都合よく意訳され)、最初の格言が魔誕生したのではないか、とのことです。
当該サイトによると、現時点で調べうる初出は1966年、マレーシア教育ジャーナルだったそうです(笑)。
—
これに限らず、ビジネスの世界でもよく目にする「誰々曰く」的な格言は、実は元の文章から改変されていたり、大元の文脈から逸脱した意味をのちに付与されて独り歩きしたりしていることがあります。最も有名なのは「PDCA」にまつわるあれこれですね。興味を持たれた方は以下の解説をご覧ください。
ある格言的なフレーズを目や耳にして、深い、なるほど、とついつい人に伝えたくなるものです。
ですが、原文を表面的に勝手に解釈して、違う意味を与えてしまっては、限りなくフェイクになってしまいます。なので、伝えるその前に、「本当だろうか?」「出典ははっきりしているんだろうか?」「元々の意味と現在使われている意味に違いはあるんだろうか?」など疑問に思い、自分なりに調べて納得することは大事だ、と、最近ますます強く感じているのでした。

松林 弘治 / リズマニング代表
大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期過程修了、博士後期課程中退。龍谷大学理工学部助手、レッドハット、ヴァインカーブを経て2014年12月より現職。コンサルティング、カスタムシステムの開発・構築、オープンソースに関する研究開発、書籍・原稿の執筆などを行う。Vine Linuxの開発団体Project Vine 副代表(2001年〜)。写真アプリ「インスタグラム」の日本語化に貢献。鮮文大学グローバルソフトウェア学科客員教授、株式会社アーテックの社外技術顧問を歴任。デジタルハリウッド大学院講義のゲスト講師も務める。著書に「子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい」(KADOKAWA)、「プログラミングは最強のビジネススキルである」(KADOKAWA)、「シン・デジタル教育」(かんき出版)など多数。


 【メタエンジニアの戯言】誰に向かってどう伝えるか、の難しさ
【メタエンジニアの戯言】誰に向かってどう伝えるか、の難しさ 【メタエンジニアの戯言】「感想を噛み締め、批判から学ぶ」
【メタエンジニアの戯言】「感想を噛み締め、批判から学ぶ」 【メタエンジニアの戯言】あえてChatGPTを使わずに新言語をさわる
【メタエンジニアの戯言】あえてChatGPTを使わずに新言語をさわる 【メタエンジニアの戯言】今年もまた小学生に多く教えられる
【メタエンジニアの戯言】今年もまた小学生に多く教えられる 【メタエンジニアの戯言】「写経」と「ティンカリング」
【メタエンジニアの戯言】「写経」と「ティンカリング」 【メタエンジニアの戯言】「獅子の子落とし」と「種まき」のジレンマ
【メタエンジニアの戯言】「獅子の子落とし」と「種まき」のジレンマ