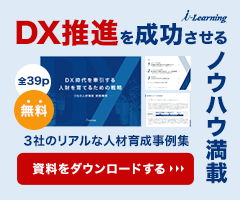アジャイルクロストーク:恐竜から学ぶ進化と適応の本質
2025.02.26アジャイル , お役立ち情報
「アジャイルクロストーク」は、アジャイルに関する知識や実践の共有を目的とした対談シリーズです。リーダーや専門家をお招きし、現場での経験や課題、最新のトレンドについて深く掘り下げながら、アジャイルの本質を探求していきます。
第1回となる今回は、ITプレナーズの最上氏をゲストに迎え、恐竜をユニークなメタファーとして活用しながら、「アジャイルがどのように変化への適応を支え、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するのか?」をテーマに議論を展開しました。
VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代に直面してテクノロジーの進化がますます加速する中、組織や個人に求められるのは柔軟性とスピード感です。本対談では、DXやデジタル技術の活用、オンライン研修やリモートワークなど、変化に適応し続ける企業の事例も交えながら、「ダーウィンの進化論」をヒントに、適応力の重要性について紐解きます。環境の変化に対応し続けるための「進化」の本質とは何か ―― その答えに迫る内容です。
アジャイルを実践している方はもちろん、これから学びたい方にも役立つ内容となっています。ぜひ、この対談を通じて、アジャイルの可能性と、私たちが次に進むべき道を考えるヒントを見つけてみてください。
《 ゲスト 》
株式会社ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック 取締役 最上 千佳子 氏
システムエンジニアとしてオープン系システムの設計、構築、運 用、教育など幅広い経験を積む。2008年に日本クイント株式会社に入社。 2012年、日本クイント株式会社の代表取締役に就任。ITプレナーズジャパン・アジアパシフィックとの統合を経て、現職。ITSM、アジャイル、DevOps等、ITをマネジメントという観点から強化しビジネスの成功に貢献するための、人材育成と組織強化のコンサルティングに従事。
用、教育など幅広い経験を積む。2008年に日本クイント株式会社に入社。 2012年、日本クイント株式会社の代表取締役に就任。ITプレナーズジャパン・アジアパシフィックとの統合を経て、現職。ITSM、アジャイル、DevOps等、ITをマネジメントという観点から強化しビジネスの成功に貢献するための、人材育成と組織強化のコンサルティングに従事。
著書:「ITIL® はじめの一歩 スッキリわかる ITIL の基本と業務改善のしくみ(翔泳社)」、「ITIL®4 の教本 ベストプラクティスで学ぶサービスマネジメントの教科書(翔泳社)」
《 MC 》
株式会社アイ・ラーニング 研修企画開発プロデューサー 阿部 仁美
日本アイ・ビー・エム株式会社にて、SW新製品開発 / ITシステム開 発のプロジェクト・マネジャー、プロジェクト・レビュー、および日本アイ・ビー・エム社全体のプロジェクト・マネジャーの育成・認定等に30年以上従事。情報処理推進機構 (IPA) にて人材育成に携わった後、楽天モバイル株式会社にてPMO:新製品開発プロセス策定 / 強化に取り組む。2022年より現職。DX の構造における①ベンダー企業②官③事業会社の3つの視点の業務を経験。
発のプロジェクト・マネジャー、プロジェクト・レビュー、および日本アイ・ビー・エム社全体のプロジェクト・マネジャーの育成・認定等に30年以上従事。情報処理推進機構 (IPA) にて人材育成に携わった後、楽天モバイル株式会社にてPMO:新製品開発プロセス策定 / 強化に取り組む。2022年より現職。DX の構造における①ベンダー企業②官③事業会社の3つの視点の業務を経験。
研修企画開発プロデューサー(専門分野:アジャイル&プロジェクトマネジメント) Registered Scrum Master (RSM)®、Project Management Professional (PMP)®
■ 二人の出会い
阿部:このたび、アジャイルクロストークを始めました。アジャイル領域のリーダーや有識者をお招きして、さまざまなお話を伺います。初回ゲストは、ITプレナーズの最上さんです。 お久しぶりですね。1年前に登壇されたアジャイルイベント以来でしたか?
最上氏(以降敬称略): そうですね、あのイベントでお会いしました。
阿部:その姿、アジャイルイベント印象に残っていますが、どうして恐竜の姿なんですか?

最上: 恐竜は今存在しませんよね。絶滅してしまいました。それは、天変地異などの変化に対応できなかったからだと思うんです。変化に適応する力があれば生き残れる——そのことを伝えたくて、この姿でアジャイルの話をさせていただきたいと思っています。
阿部: 恐竜が生き残るために戦ったように、私たちも厳しい冬のなかでも生き残っていきたいと思っています。
最上:そうですね、一緒に生き残りましょう!
■ 身の回りのアジャイル
阿部: 最上さん、現在の企業やビジネスで、変化に適応して成功した例として、どんなものがありますか?
最上:最近の話題でいえば、やはりコロナによる大きな変化が 、我々のような研修業界にも影響を与えたと感じます。以前は講師と受講者が1つの教室に集まり、対面で研修を行うのが一般的でしたが、コロナを契機に研修のスタイルがリモート研修へと大きく変わりました。これは、環境の変化に適応した一例だと思います。リモート研修が普及したことで、講師にも受講者にも新たな可能性が広がっています。また、リモート会議やリモートワークが一般的になり、働き方そのものにも大きな変化が生まれています。
、我々のような研修業界にも影響を与えたと感じます。以前は講師と受講者が1つの教室に集まり、対面で研修を行うのが一般的でしたが、コロナを契機に研修のスタイルがリモート研修へと大きく変わりました。これは、環境の変化に適応した一例だと思います。リモート研修が普及したことで、講師にも受講者にも新たな可能性が広がっています。また、リモート会議やリモートワークが一般的になり、働き方そのものにも大きな変化が生まれています。
阿部:確かに。変化を乗り越えた例ですね。日本全国の講師の方々が場所に縛られることなく講義できるようになり、受講者も全国や海外から参加できるようになりオンライン化には多くのメリットがありますね。移動も不要となり、時間や交通費なども節約してより有効活用できるようになりました。私たち女性にとってもより働きやすい環境になったと言えますね。他にも、最近では銀行や旅行代理店の変化も大きいですよね。
最上:確かに。ネットバンキングの普及により、銀行の店舗が次々と減少し、集約される動きが進んでいます。私の近所でも銀行の支店やATMが姿を消しました。同様に、旅行代理店も変化しました。以前は店舗で相談して予約するのが一般的でしたが、今ではスマホで簡単に予約ができる時代です。ATMも減少傾向にあり、送金もアプリで手軽に済ませられるようになりました。昔なら「そんなの無理」と思われていたことが、今では当たり前になっているのが印象的ですね。
阿部:それも変化への適応の一環ですね。例えば、現金を使わずにスマホで支払いが完結する便利さも、大きな変化だと思います。
最上:こうした変化はゲーム業界にも大きな変化が見られます。特にゲームの世界は、まさにアジャイルな考え方を体現していると感じます。昔のゲームは、完成品をカセットにして提供する形が主流でしたが、最近のオンラインゲームはリリース後も進化を続けています。思いもつかないような新しいフィールドができたり、新しいキャラクターや武器が追加されるなど、終わりのない楽しみを提供しているのが特徴です。昔は、できたものをしっかりテストしてから出すというのがキホンのキだったのですが、今は出してから成長させていっています。それも、作り手が勝手に作るのではなく、ユーザーの利用状況とか、SNSなどのフィードバックを分析し、必要な要素を取捨選択してゲームに反映しているのです。こうした取り組みを通じて、ユーザーの期待に応え続け、飽きさせない工夫が求められています。
阿部:まさにアジャイルな発想ですね。これがゲーム業界だけでなく、他の業界にも広がっているんでしょうか?
最上:はい、特に自動車業界ではテスラがその代表例です。ソフトウェアの進化はもちろんですが、ハードウェアの開発でもアジャイルの考え方を取り入れています。利用者のニーズに迅速に応えることを目指している点では、ソフトもハードも区別がありません。ユーザーの声をもとに製品を改良し続ける姿勢が求められています。
阿部:これからのものづくりは、まさにユーザーの声を反映し続けることが求められるということですね。
最上:その通りです。昔は不可能だと思われていたことも、今では技術の進化によって実現可能になっています。それに伴い、利用者の期待もどんどん高まっています。それが企業の変化をさらに加速させている要因の一つだと思います。
■ DXにアジャイルは必要か
阿部:最上さん、最近よく耳にするDXですが、その中でもアジャイルの重要性が特に注目されていますよね。経済産業省のDXレポートで話題になった「2025年の崖」についても、改めてその定義をおさらいしてみたいと思います。定義が少し長くて難しく感じますね。特に「デジタル技術」に注目したいのですが、これを使うだけでDXだと考える方も多いですよね。

最上:確かにDXの「D」はデジタル技術を指しますが、見落とされがちなのが「X」、つまりトランスフォーメーション(変革)を意味する部分です。経済産業省の定義でも、デジタル技術だけでなく、変革の重要性が強調されています。「DXって結局、デジタル化のことだよね?」とか、「電子化は昔からやっているから、これ以上変える必要はないのでは?」という意見もありますが、それは本質を捉えきれていません。デジタル化には段階があり、まずは手書きや印刷物の情報をデジタルデータに変える「デジタイゼーション」があります。例えば、フィルムカメラからデジタルカメラに変わることがその一例です。そして次に「デジタライゼーション」という段階があり、これは単なるデジタル化とは異なる次元の話です。

阿部:なるほど。「デジタイゼーション」はアナログ情報をデジタル化することですね。その次が「デジタライゼーション」ですね。
最上:「デジタライゼーション」とは、デジタル技術を活用して業務プロセスそのものを変えることを指します。例えば、デジタルカメラの導入で、フィルムを現像してアルバムに差し込む手作業が、デジタルデータを保存するプロセスに変わるようなケースです。このように作業の流れや内容がデジタル化の結果として変わるのが「デジタライゼーション」です。しかし、これだけではDXとは言えません。DXはさらにその先の変革を意味しています。 例えば、SNSではスマホで撮った写真をすぐアップして拡散したり、それを広告に活用するのが普通ですよね。これってデジタル化を超えて、データや思考の使い方が変わった証拠です。こうした変化によって新たなビジネスが生まれたり、新しいコミュニティが形成されたりするのも、DXの重要な側面です。効率化にとどまらず、社会やビジネスを変革するのが DX です。
例えば、SNSではスマホで撮った写真をすぐアップして拡散したり、それを広告に活用するのが普通ですよね。これってデジタル化を超えて、データや思考の使い方が変わった証拠です。こうした変化によって新たなビジネスが生まれたり、新しいコミュニティが形成されたりするのも、DXの重要な側面です。効率化にとどまらず、社会やビジネスを変革するのが DX です。
阿部:SNSは、多くの人が写真を投稿するだけでなく、新しい友人関係やコミュニティを生み出しています。そして、企業はその場を利用して、新たな製品やサービスを提供していますよね。それが新しいビジネスモデルを作り出している。さらに、投稿された情報を活用してユーザーのプロファイルを取得し、それを元にしたマーケティングを行う企業が市場で優位に立っていますよね。
最上:これからの時代、発想の転換がますます重要になります。最近「ワカメ」について調べたところ、翌日からSNSにワカメの商品広告が次々と表示されるようになったんです。最近では、こうした広告のターゲティングにAIと機械学習が活用されるケースも増えてきました。このような時代にDXを成功させるには、アジャイルが非常に重要です。市場や顧客の声を迅速に反映し、変化に対応できる企業こそがDXを実現できるのです。
阿部:本当に最近よくありますよね。まさにアジャイルとDXは密接に繋がっていて、ユーザーのニーズに素早く対応し、フィードバックを次のアクションに活かす柔軟さが求められますよね。
最上:その通りです。アジャイルでは、自己組織化や自律性が重要で、自分で考え、判断し、お客様のために最適な行動を取ることが成功の鍵です。さらに、その姿勢を認めて後押ししてくれる上司や経営者がいる企業は、より一層強くなります。
■ 経験主義 or 学習
最上:年次が上がると、日本では年上や経験豊富な人が正解を持っていると思いがちですよね。でも、時代は変化していて、一番最先端を知っているのは若者、特に女子高生かもしれません。
阿部:確かに、経験を積んだ人ほど新しい考えを受け入れにくくなることもありますよね。だからこそ、若者や新しいことから学ぶ姿勢が大事だと思います。
最上:大事ですよね。「アンラーン(unlearn)」という言葉が注目されていますが、これまでの常識や成功体験を一度リセットする必要があります。ただ、それが難しいんですよね。

阿部:難しいですね。でも、本当に成功している人ほど謙虚で、新しいことに耳を傾けていますよね。「昔はこれで良かったけど、今は違う」と認める姿勢が素晴らしい。
最上:そういう方って、まさに「実るほど頭を垂れる稲穂」ですね。
阿部:卒業したら勉強しなくていい、働けばいいんじゃなくて、働いていても、例えば会社を辞めても学ぶことってずっと続けて良いと思うんですよね。それによって自分がどんどん成長していく、死ぬまで成長していく。それがライフロングラーニングだと思いますし、やっぱりアジャイルの考え方に近いですよね。
最上:学び続けないと、人生がつまらなくなりますもんね。
阿部:そう、つまらないです。
■ 実践が先? 勉強が先?
阿部:最上 さん、ライフロングラーニングで学び続けたいと思っているんですが、アジャイルには学ぶことが多いですよね。ちなみに、アジャイルを始めようと思ったら何から始めるのがいいのでしょうか?研修もありますが、どうやってスタートするのがお勧めでしょうか?
さん、ライフロングラーニングで学び続けたいと思っているんですが、アジャイルには学ぶことが多いですよね。ちなみに、アジャイルを始めようと思ったら何から始めるのがいいのでしょうか?研修もありますが、どうやってスタートするのがお勧めでしょうか?
最上:よく聞かれる質問ですが、簡単に言うと方法は2つあります。一つは『とりあえずやってみる』というアジャイルの基本である経験主義に基づく方法です。失敗してもまた挑戦する形ですね。もう一つは、最低限の知識を学んでから始める方法です。どちらも学びとして有効ですが、どの方向で試すべきかわからない場合は、まず知識を得るのが良いです。例えば、アジャイルで最も有名なスクラムというフレームワークをまとめた『スクラムガイド(※)』があります。12 ページほどで無料でダウンロードできるので、それを読んで試してみるのがおすすめです。
阿部:何も知らないまま始めるより、基礎を理解してからスタートした方が良いと思うんです。でも、形だけ真似しても意味がないと感じることが多いんですよね。本質、つまり「なぜこれが良いのか」という目的や本質を理解するのが大事だと思うんですけど、その点どう思いますか?
最上:はい。形から入ることが多いですが、目指すゴールを意識して形を活用しないといけないですね。それはアジャイルに限らず、どんな分野にも言えると思います。
阿部:フィードバックがなぜ重要なのか、なぜそのやり方でスピードが上がるのかといった本質を理解せずに、ただ『とりあえずスクラムを回す』だけでは意味がありませんよね。だからこそ『守破離』が大事で、基本の『守』の段階で本質的な目的を理解することが重要だと思います。
 最上:本質を理解して納得した上で、自分たちの現場に合う形にアレンジするのが『破』で、それを基に新しい方法を探るのが『離』です。『型破り』も、型がなければ破れないので、まず『守』の段階で基礎をしっかり作ることが重要です。そのために、先ほどお話ししたスクラムガイドは、たった12ページでコアとなる基本がしっかり書かれていて、とても分かりやすいのでお勧めです。また、アジャイルの経験主義では『まずやってみよう』が基本ですから、情報が分厚すぎるより、最低限の知識で始める方が効率的だと思います。
最上:本質を理解して納得した上で、自分たちの現場に合う形にアレンジするのが『破』で、それを基に新しい方法を探るのが『離』です。『型破り』も、型がなければ破れないので、まず『守』の段階で基礎をしっかり作ることが重要です。そのために、先ほどお話ししたスクラムガイドは、たった12ページでコアとなる基本がしっかり書かれていて、とても分かりやすいのでお勧めです。また、アジャイルの経験主義では『まずやってみよう』が基本ですから、情報が分厚すぎるより、最低限の知識で始める方が効率的だと思います。
阿部:確かに。「守」を学んだ後の「破」の部分では、企業ごとに独自のスタイルがあっていいですよね。何々社版スクラムが資産となり、風土として根付くのが理想です。
最上:そうです。形どおりにやることが目的ではなく、お客様に価値を届け続け、自分たちも進化する。それが最終的な目標で、正解が一つとは限らないのが重要ですね。
阿部:よく会社から『DX推進リーダー』としてアジャイルをやれと言われることがありますが、アジャイル自体が目的ではないんですよね。また、『どう始めたらいいか分からない』という声もよく聞きます。
最上:それで困っている方は多いですね。特に、アジャイルを広める立場の人が自分で納得していないと、周りに説明しても反発を受けやすいものです。だからこそ、『何のためにやるのか』を自分でしっかり理解し、熱意を持って伝えることが重要です。そして、周囲を少しずつ巻き込みながら進めていくのがポイントです。一気に全員を納得させるのは難しいので、小さな成功を積み重ねて仲間を増やしていくアプローチが大切です。
阿部:小さく始めて広げる考え方は大事ですよね。ジョン・コッターの『変革の8段階のプロセス』でも、チェンジリーダーが小さな変化から始めて大きな波を作るという話がありましたが、アジャイルもそれに近いと思います。変化を好まない方も多いですが、変化を『面白い』と感じたり、『どう解決しよう』と考えることで、喜びややりがいが生まれ、その結果チームや組織がより強く成長できるのではないかと思います。
最上:その通りですね。
■ まとめ
阿部:最上さん、今日アジャイルというテーマで「進化と適応」についてお話しさせていただきました。
最上:変化に対応しなきゃいけないとか、DXの重要性などいろいろお話しましたね。
阿部:デジタイゼーション、デジタライゼーション、そしてデジタルトランスフォーメーション。この流れをしっかりと捉え、2025年の崖を乗り越え、大きくジャンプして生き残りたいですね。
最上:恐竜も裸足で走るだけじゃなく、スマホを持 ったりSNSを活用したり、変化していきたいですね。
ったりSNSを活用したり、変化していきたいですね。
阿部:学び続けながらですね。また一緒に楽しみながら進んでいければと思います。本日はありがとうございました。
最上:ありがとうございました。
■ おわりに
阿部:いかがでしたでしょうか。
「アジャイルクロストーク Vol.1 恐竜から学ぶ進化と適応の本質」を通じて、アジャイル思考の重要性や変化への適応力について、多くの示唆を感じていただけたのでしたら幸いです。恐竜というユニークなメタファーを用いながら、DXの推進や企業の変革、個人の成長について掘り下げてきました。変化に適応できない企業や個人は取り残される可能性がありますが、「学び続ける力」と「進化する意志」を持つことで、持続的な成長が可能になります。アジャイルはソフトウェア開発に限らず、組織運営や個人のキャリア形成にも活かせる考え方です。「まずはやってみる」ことから始め、経験を学びに変え、成長につなげていきましょう。
最後に今日の言葉、アジャイル川柳・アジャイル標語を考えてみました。
阿部からは「生き残れ! 変化に適応 今日からアジャイル」
それを受けて最上さんから「進化とは 変化を楽しむ のが極意」といただきました。本記事がアジャイル実践の一歩となれば幸いです。
次回の「アジャイルクロストーク」もどうぞお楽しみに!

[ スクラムガイド (※)](2020年 11月版)
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Japanese.pdf
「YouTube チャンネル アジャイルクロストーク」※実際の対談をご視聴いただけます
https://www.youtube.com/@agilecrosstalk
[ アジャイル研修 ]
https://www.i-learning.jp/project-management/agile/
[ プロジェクトマネジメント研修 ]
https://www.i-learning.jp/courses/projectmngmnt/pm/


 メンバーを牽引するチームリーダーの役割とは?
メンバーを牽引するチームリーダーの役割とは? オンライン研修とは?オンライン研修のコツ
オンライン研修とは?オンライン研修のコツ ニューノーマルとは?ポストコロナ時代の新たな働き方とその課題
ニューノーマルとは?ポストコロナ時代の新たな働き方とその課題 新人エンジニアに求められる学び続ける力と論理的思考力 〜インプル社が語るAI時代に必要なスキル〜
新人エンジニアに求められる学び続ける力と論理的思考力 〜インプル社が語るAI時代に必要なスキル〜 デジタル人材未来塾 第一回未来交流会 レポート:未来をデザインするDNA 〜2030年のテクノロジー・社会・顧客
デジタル人材未来塾 第一回未来交流会 レポート:未来をデザインするDNA 〜2030年のテクノロジー・社会・顧客 未来塾 エバンジェリスト インタビュー:「正解より“問い”を持つ力を」未来を創るリーダーに求められる思考とは
未来塾 エバンジェリスト インタビュー:「正解より“問い”を持つ力を」未来を創るリーダーに求められる思考とは