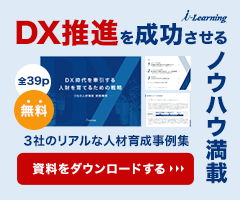【メタエンジニアの戯言】忘れる脳、捏造される記憶、そして温故知新
2025.04.08松林弘治の連載コラム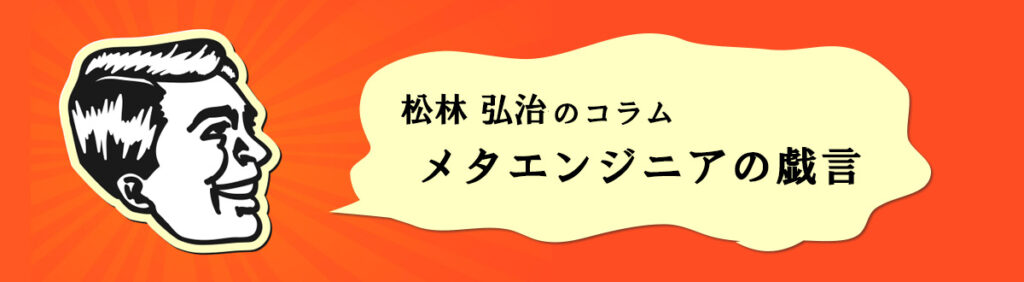
「人間は忘れる生き物である」、と言ったとされるのは、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウス(1850-1909)という人です。
彼の先駆的な研究で最も有名なのは「忘却曲線」で、人間は記憶した直後から急速に忘れ始め、20分後、1時間後、1日後と時間が経つにつれ、記憶の多くを失っていき、覚え直すコストが増大する、というものです。しかし、記憶直後から反復的に再学習を行うことで、忘却速度を遅くでき、記憶の定着率は高まることも明らかにされています。
詳細な解説は書籍やwebの情報を参照していただくとして、これらの話は学習塾業界や社員教育の分野でも頻繁に言及されてきたため、「忘却曲線」「節約率」といった用語を耳や目にしたことのある方も多いでしょう。
ーーー
そんな「忘れる動物」である我々人間は、悲しいかな、数日前や数週間前のことですら、きれいさっぱり忘れてしまいがちです。挙げ句の果てには、つい数分前に見たことや考えていたことを思い出せなくなることも増えてきたりと、己の齢をいやがおうでも認識させられます。
さらに数年〜数十年と年月が経つと、記憶は他の経験や情報と混ざり合い、事実とは異なるかたちに変容することもしばしばです。この「過誤記憶(虚偽記憶)」という現象は、自覚なく私たちの記憶を捏造し、同窓会などで昔の話が食い違ったりなんてこともあります。もしかしたら、電話や会議での「言った言わない問題」も類似の側面があるかもしれませんね。
さらには、個人の記憶を超えて、世代を超えた集団 の記憶に至っては、さらに問題が複雑化します。社会や時代の価値観によって記憶が再解釈され、事実や背景、ニュアンスが変化して伝わることも頻繁に起こります。時には、事実と反する解釈が(意図せずにか、確信犯的にか、の差はあれ)流布されることも珍しくありません。
の記憶に至っては、さらに問題が複雑化します。社会や時代の価値観によって記憶が再解釈され、事実や背景、ニュアンスが変化して伝わることも頻繁に起こります。時には、事実と反する解釈が(意図せずにか、確信犯的にか、の差はあれ)流布されることも珍しくありません。
ーーー
だからこそ、「歴史」や「系譜」、例えば「技術史」や「文化史」などを学ぶ意義があるのだと考えます。
例えば、今私たちが日常的に使っているさまざまなツールやサービスが登場する以前、人々はどのように工夫を凝らしていたのか、それが登場したことでどのような変化がもたらされたのか、という視点を持つことで、現代の便利なツールの価値を再認識できます。
小学校での授業で児童たちと接すると、彼らの生きる時代と私たちが育った時代の違いに改めて気付かされます。物心ついたときからスマホやタブレットが身近にあり、インターネットやGPSがどこでも使えて当たり前。書店や図書館に行かなくても手元で大量の情報を簡単に検索可能。テレビというスケジュールが決められた一方向のメディアではなく、オンデマンドかつ双方向性を備えた動画配信サービスに慣れ親しんでいる。そんな世代の多くは、ブラウン管ディスプレイ、ファックスはおろかCDやMD、フロッピーディスクなど存在すら知らない(なのにカセットテープやレコードは知ってたりする)、なんてことも珍しくありません。
ーーー
そんな児童たちに、2000年頃の「スリムPC」の実物を見せると、みな一様に驚き、中をあけてドライブや基板などを見せるとますます興奮で目を輝かせます。一方で、児童たちが毎日使っているGIGA端末の中にも、より高度に集積化された同様の技術が詰め込まれていることにはあまりピンと来ていないようです。ここには現代技術の「ブラックボックス化」による影響が感じられます。
児童から「江戸時代の人たちはどうやってLINEをしていたのか」「なぜ昔のゲームはドットが大きくてカクカクしたものが人気だったのか」など、微笑ましい質問を受けるたびに、思うことがあります。
人類の叡智の長年の積み重ねにより、超高速で正確な計算・処理を可能にし、それが手のひらサイズの端末にまで進化し、身近でありふれた存在となっている。その上で動作するソフトウェアやサービスも、長い試行錯誤と淘汰の歴史を経て今の姿となっている。そして、今後も間違いなく変わり続け、より新しいものが生み出されていく。
そのようなことを多少なりとも意識した上で、現代の便利なツールを活用する人が増えてほしいし、過去を踏まえて新しいものを生み出していって欲しいものです。
「忘れる」ことが人間の宿命なのであれば、「学び直す」ことは我々の使命と言えるかもしれません。今を急ぐ私たちだからこそ、論語(為政篇)で孔子が語ったとされる「温故知新」のように、先人の工夫や失敗を学びとることで、知識のバトンをつなぎ、より豊かな未来を創造していけるのでは、と思います。

松林 弘治 / リズマニング代表
大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期過程修了、博士後期課程中退。龍谷大学理工学部助手、レッドハット、ヴァインカーブを経て2014年12月より現職。コンサルティング、カスタムシステムの開発・構築、オープンソースに関する研究開発、書籍・原稿の執筆などを行う。Vine Linuxの開発団体Project Vine 副代表(2001年〜)。写真アプリ「インスタグラム」の日本語化に貢献。鮮文大学グローバルソフトウェア学科客員教授、株式会社アーテックの社外技術顧問を歴任。デジタルハリウッド大学院講義のゲスト講師も務める。著書に「子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい」(KADOKAWA)、「プログラミングは最強のビジネススキルである」(KADOKAWA)、「シン・デジタル教育」(かんき出版)など多数。


 【メタエンジニアの戯言】古くて新しい、小さく大きな DX
【メタエンジニアの戯言】古くて新しい、小さく大きな DX 【メタエンジニアの戯言】誰に向かってどう伝えるか、の難しさ
【メタエンジニアの戯言】誰に向かってどう伝えるか、の難しさ 【メタエンジニアの戯言】「ググり力」は古来からの必須スキル?
【メタエンジニアの戯言】「ググり力」は古来からの必須スキル? 【メタエンジニアの戯言】「論理的思考力を育てる」方法はあるのか?
【メタエンジニアの戯言】「論理的思考力を育てる」方法はあるのか? 【メタエンジニアの戯言】「名もなき家事」と論理的思考力
【メタエンジニアの戯言】「名もなき家事」と論理的思考力 【メタエンジニアの戯言】AI時代だからこそ必要な論理化・言語化スキル
【メタエンジニアの戯言】AI時代だからこそ必要な論理化・言語化スキル