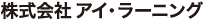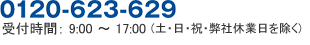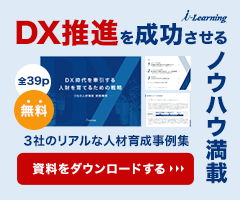プロジェクトマネジメント研修事例:住友商事株式会社
2025.08.22育成事例事業会社の強みを活かし、最強のDX人材を育成するプロジェクトマネジメント研修

竹川 奈緒(右)
自動車流通DXユニット DX Labチーム チーム長
前職では外資系IT企業で、製造業向けコンサルティングやシステム構築を担当。2024年に住友商事へキャリア入社し、自動車流通DXユニットのDX Labチームのリーダーとして、自動車流通事業のDXを推進。営業現場の課題を分析し、業務改善の方針決定から実際のシステム開発まで、DXプロジェクト全体の推進に携わるチームを牽引する。
福井 盛之(左)
自動車流通DXユニット Development & Operationsチーム チーム長代理
プロジェクトマネージャーの一人として、リビアの車両販売システムの開発を担当。現地事業会社、ユーザー、インドネシアのベンダーとのコーディネーションに携わる。
岩渕 加那子(中央)
自動車流通DXユニット DX Labチーム 主任
ウクライナ向けのトレードシステム開発の業務リーダーとして、出荷処理・在庫管理システム開発のプロジェクトマネジメントを担当。
――はじめに、お三方の仕事やミッションについて教えてください。
竹川氏:私たちは住友商事の自動車グループ内にある、自動車流通DXユニットに所属しています。完成車を卸売する事業のIT技術による事業変革や業務改善、いわゆるDX推進が主なミッションです。さらに流通DXユニットには大きく2つのチームがあり、その1つが私と岩渕が所属するDX Labチームです。現場の課題を拾い上げ、改善の方針を策定するミッションを持っており、私はリーダーを務めています。もう1つのチームは福井が所属するシステム開発・運用チームで、DX Labチームが策定した方針に基づいて要件定義からシステム構築、現場への導入業務を担っています。
福井氏:私はシステム開発・運用チームで、リビアにある企業の車両販売システムの開発に携わっています。事業会社やエンドユーザー、さらにはインドネシアのベンダーをコーディネーションし、ユーザーが本当に必要としているシステムを届けることを目指しています。
岩渕氏:私はウクライナ向けのトレード業務に使用する出荷処理や在庫管理システムの開発で業務リーダーを担当しています。戦時下のウクライナでは避難用車両の需要があり、出荷オーダーは増加しています。システムで流通がスムーズになれば、より多くの需要に応えられると感じています。
アイ・ラーニングを選んだ経緯と背景

――アイ・ラーニングとのお付き合いが始まったきっかけや時期について教えてください。
竹川氏:アイ・ラーニングとのお付き合いは、2024年6月ごろのプロジェクトマネジメントスキル習得計画段階からです。当時の自動車流通DXユニットではプロジェクトマネジメントの経験者が少なく、実務をしながら手探りで学んでいる状態でした。そのなかで、ITベンダーとの折衝で共通認識を持ちづらいことが課題となり、課題解決の施策としてプロジェクトマネジメント研修の実施を考えるようになりました。
――アイ・ラーニングを選んだ決め手は何だったのでしょうか?
竹川氏:アイ・ラーニングを選んだ決め手は2つあります。1つはケーススタディが充実していること。というのも、システム開発の経験がない弊社メンバーがすぐにプロジェクトの現場に適用できるよう、疑似体験ができるケーススタディ中心の研修を求めていたのです。そしてもう1つは教科書的な「あるべき論」に留まらない、実務経験が豊富な講師から研修を受けられること。私自身も過去にアイ・ラーニングの研修を受講した経験があり、ケーススタディと実体験で構成されている研修内容が実務で役立った実感を持っていたため、アイ・ラーニングの導入を決めたという流れですね。
研修の企画・実施
――プロジェクトマネジメント研修を企画された背景や目的について教えてください。実際にどのような形で行われたのですか?
竹川氏:
DXにおいて重要なのは、実はIT知識よりも、業務に関する知識やその本質を理解することだと考えています。あたりまえですが、実際に業務に携わっている私たち事業会社の人間は、誰よりも業務知識を持っていますし、業務プロセス一つ一つを理解しています。そこにシステム開発やプロジェクトマネジメントの知識が加われば、鬼に金棒だと思います。
現場を知る人が、業務の中で感じた課題解決やこんなことができたらいいなという要件を自ら発案して企画し、システム開発の推進までやりきれたら最強のDXを実現できると思います。この研修は、事業会社が主導するDXをめざして企画したものです。
今後は、事業会社の立ち位置でDXを推進する人材はどういう人で、どのようなキャリアプランがあり、どのように育成していくかといったところを含めて考えていきたいと思っています。

研修を導入したのは、プロジェクトマネジメント経験のないメンバーを一人ひとりサポートするよりも、研修で知識の底上げを図ることでチーム全体の戦闘力が効率良く高まると考えたからです。
研修の形態としては、アイ・ラーニングの講師に来社していただき、受講者は10名ずつで2回に分けて実施しました。1回目は、すでにプロジェクトマネジメントに携わっているDXユニットメンバーのみ、2回目は今後プロジェクトマネジメントに携わるDXユニットの新メンバー5人と営業チームからの5人という構成です。当初は2回に分ける予定はなかったのですが、1回目の受講者から「営業メンバーや海外派遣される人にも役立ちそう」という意見があったため、メンバーを変更して2回目を実施することになりました。
――研修内容としてはプロジェクトを成功に導くための基礎研修だったのでしょうか?
竹川氏:弊社では、カスタマイズしたプロジェクトマネジメント研修を実施してもらいました。一般的なプロジェクトマネジメント研修では、IT開発経験者やエンジニアがおもな受講対象ですが、弊社の受講メンバーはエンジニア職ではありません。また同じプロジェクトマネージャーでも、ITベンダーとユーザーである事業会社とでは見るべき視点が異なります。
弊社が目指すのはITベンダーと対等にコミュニケーションを取り、事業会社の目線でプロジェクトを推進できる人材です。そのような人材を育成できるよう、研修のカスタマイズが必要だと考えたのです。
――課題感に合わせて研修内容をカスタマイズされたのですね。研修の実施やカスタマイズにあたって、大変だったことはありますか。
竹川氏:もっとも難航したのは日程調整ですね。海外出張が多いメンバーの予定と、講師の予定を調整するのがかなり大変でした。
カスタマイズ内容面の調整は非常にスムーズでした。弊社の要望にマッチする提案を複数していただき、そのなかから最適なものを選択して、内容を詰めるという作業を行いました。的確なアドバイスをもらいながらすり合わせができたので、2、3回の打ち合わせで研修内容が固まりました。
研修の内容と効果・感想
――研修の具体的な内容と受講した感想などを聞かせてください。
竹川氏:研修はプロジェクトの立ち上げから、実行・終結までの一連の流れを学ぶ構成になっています。テーマごとに座学とケーススタディを反復する形で進行し、グループワークでの思考や議論を通して、学んだことをより深く吸収していくコンテンツでした。
福井氏:特に、座学で学んだ理論とケーススタディを反復する形が良かったと思います。もちろんグループワークでの議論も良い刺激になりましたが、やはり経験豊富な講師による講義は実務にすぐに活かせる内容で素晴らしかったです。座学で学んだことを実践で活用する際の注意点や関係各所との調整方法など、今まさに直面している課題にかかわる内容でした。さまざまな国籍の方とのコーディネーションが必要な立場として、非常に勉強になりました。
岩渕氏:スケジュール作成やリスクの洗い出しなどのグループワークも、実践的で勉強になりましたね。経験則による感覚的な部分も含めて、わかりやすく伝えてくださったので、研修内容にも納得感が増してイメージしやすくなりました。
――研修後に効果を実感する場面や仕事への影響はありましたか。

岩渕氏:研修を受けてから、ITベンダーとの進捗会議において内容の解像度が高まりました。私自身まだまだわからない用語も多く、把握するだけでも時間がかかっていたのですが、研修後は「リスクの洗い出し」や「広い視点でのスケジュール調整」など、リーダーとしてチェックすべきポイントや疑問点をより深堀りできるようになりました。
実は研修に参加した時期が、担当プロジェクトが開発フェーズに入るタイミングと重なっていたのですが、それまでの経緯を研修内容に照らして見直したところ、「こういうことだったのか」と理解が深まりました。
福井氏:個人的な最大の収穫は、プロジェクトを進めるための「物差し」を身に付けられたことだと思います。
私は2024年5月からDXユニットに参加していますが、現場の業務知識やシステムの使い方などについては十分理解していた一方、開発側の視点や考え方は身に付いていませんでした。そのため、システム開発にとってどの部分がマストで、どこからがベターで、どこが必要ないのかなどをうまく切り分けられなかったのです。
ところが研修の受講後は、システム開発の目線で「絶対に必要な部分」と「譲れる部分」をよりスピーディに判断できるようになりました。その結果、課題も明確になり、以前よりテンポ良くプロジェクトが進み始めましたね。各所とのコミュニケーションも円滑になりました。色々と予想外の難題や課題にも直面するため、まだまだ試行錯誤で進める部分も実際にはありますが、お互いに最適な場所・速度でボールを投げ合うようなやり取りを目指して日々システム開発に取り組めています。
今後の展望とアイ・ラーニングへの期待
――今後のプロジェクトマネジメント研修、人材育成についてはどのように考えていますか。そのなかでアイ・ラーニングへの期待があれば聞かせてください。
竹川氏:今後も新規プロジェクトに参加する際には、今回のようなプロジェクトマネジメント研修を実施したいと考えています。受講後、実務経験を積んだメンバーからは「提案や見積もり内容も評価できるようになりたい」「UATの計画・ケース作成の方法を学び品質を高めたい」といったより具体的な要望も出ており、現在はより専門性の高い研修も検討している段階です。
育成の視点では、課題を掘り下げる領域の重要性と、事業会社のDX人材の強みを意識しています。私たち事業会社の人間は、ITベンダーよりも自社の業務に精通しています。現場をよく知る私たちがシステム開発の知識を身に付けることで、もっとも効率良くDX推進をリードしていけると考えています。そのために求められるスキルやキャリアプラン、育成方針などを定義して、人材育成に取り組みたいですね。
そのためにも、ほかにどのような研修が適しているか、育成ステップをどう組むべきかなど、アイ・ラーニングには人材育成全般の相談に乗っていただければと思います。
最強のDX人材育成への道
――最後に、同じように人材育成に取り組んでいる企業や学びを必要としている方へのメッセージをお願いします。
竹川氏:システム開発やDXでは、事業会社とITベンダー双方が歩み寄る形でプロジェクトを牽引できるのが理想です。しかし、実際は事業会社側にシステム開発の知識がないために対等に議論できない、任せっぱなしになるといった課題が発生しがちです。アイ・ラーニングのプロジェクトマネジメント研修で得られる知識があれば、ITベンダーと対等にコミュニケーションを取れるようになると思います。
システムによる利益を享受するのも、最終的なリスクや損害を受けるのも、私たち事業会社です。そのため、ITの専門家であるベンダーとの話し合いのなかでも譲れない部分はしっかり主張し、議論するためには最低限の知識が必要だと考えています。
福井氏:IT・DXはビジネスの基盤になりつつありますので、業種や職種を問わず、受講するメリットはあると思います。特に、海外案件では言語や商習慣の違いからくるギャップが生まれやすい中、グローバルに推奨されているプロジェクトマネジメントの基礎知識を体系的に理解することは、私の中で海外ベンダーや外国人の社内専門家とスムーズに議論できる土台となりました。
あらゆる業務でいえることですが、システム開発でも些細な認識の違いが後々大きなギャップになる場合があります。海外や異業種などを相手に仕事をする方で、市場で戦う基礎力を身に付けたいと考えているならアイ・ラーニングの研修はおすすめですね。
岩渕氏:業務システムの開発を成功させるには、その業務に精通していることが必須条件ですが、最強のDX人材を育成するには業務の知識だけでは足りません。研修を導入して、ITやプロジェクトマネジメントの知識を身に付けることが重要です。ITプロジェクトのイニシアチブを取れる人材育成を考えている場合は、社内教育だけではなく研修もうまく活用することで会社全体の成長にもつながると思います。
●プロジェクトマネジメント研修はこちら
https://www.i-learning.jp/service/projectmngmnt.html
育成に関するお悩みや課題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
●お問い合わせフォーム
https://www.i-learning.jp/contact/
アイ・ラーニングコラム編集部


 AI、IoT時代のDX人材育成教育 研修事例:キヤノン株式会社
AI、IoT時代のDX人材育成教育 研修事例:キヤノン株式会社 全社で実践 プロジェクトマネジメント研修事例:オリンパス株式会社
全社で実践 プロジェクトマネジメント研修事例:オリンパス株式会社 ユーザー起点の発想を全社員が身につける:オープン研修活用事例
ユーザー起点の発想を全社員が身につける:オープン研修活用事例 データ活用の模擬体験から伴走支援まで:オープン研修活用事例
データ活用の模擬体験から伴走支援まで:オープン研修活用事例 ハイブリッド研修でDX推進のリーダー育成:オープン研修活用事例
ハイブリッド研修でDX推進のリーダー育成:オープン研修活用事例 DX人材育成研修事例:ビーウィズ株式会社
DX人材育成研修事例:ビーウィズ株式会社