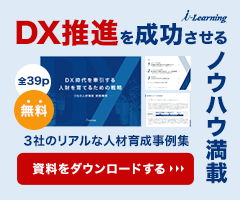【メタエンジニアの戯言】セルフオーダーシステムという手段の目的は
2025.09.08松林弘治の連載コラム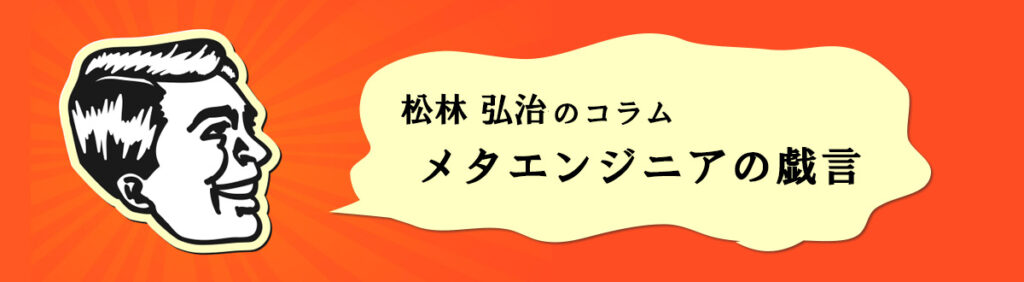
先日、久しぶりに最寄駅の某飲食チェーン店を訪れました。以前は店員に口頭で注文を伝えるスタイルだったのですが、ついにタッチパネルによるセルフオーダー式が導入されていました。席に備え付けられたタブレットから客が自分で操作して注文する、最近お馴染みのスタイルです。
昼時は特にイートイン/テイクアウト共に大変繁盛している、20席ほどの小規模なそのお店のカウンター席で注文を済ませたとき、ご高齢の女性がひとりで来店、私の隣に席をとられました。「注文はタッチパネルからお願いします」と店員に促されたその方は、要領がつかめない様子で、「どのように注文したらいいのかよく分からない」というような困惑した表情を浮かべていました。
隣にいた私が手助けをしてさしあげようかと思ったその時、店員が即座にその女性の横につきました。そして、世間話をするかのようにやさしく話しかけながらヒアリングし、代理でタッチパネル操作をしてあげていました。お客に寄り添った対応はとても微笑ましく感じられましたし、そのお客さんもとても感謝しておられました。
しかし、その一方で気になる光景も同時に目に入りました。店内の接客スタッフはその店員ひとりだけで、他は厨房スタッフのみ。すでに食事を終えた客がレジ前で会計を待ち、店外ではテイクアウト注文を行いたい客が待っていました。親切な対応が、かえって他の業務に遅延を生じさせていたのです。
ーーー
この状況を目の当たりにし、注文した食事がくるのを気 長に待っていた私は、考えをあれこれめぐらせていました。
長に待っていた私は、考えをあれこれめぐらせていました。
そもそも、「客によるセルフオーダーシステム」の導入目的は、人件費削減と業務効率化のはずです。しかし現実には、ディジタル機器に不慣れなお客様への配慮が必要となり、結果的に従来以上の人的リソースを要する場面が生まれているのです。単独のご年配層の来店がかなりあるこのお店の場合、なおさらです。
技術的な側面から考えると、タッチパネル式システムのUI/UXのさらなる改善・改良を行うことで、より幅広い年齢層が利用しやすくなるかもしれません。今回の飲食店の場合は、大人数で訪れたくさん注文する機会の多いファミリーレストランとは異なり、1つのメニューを注文される単独来店がほとんどです。そのため、メニュー数にもよるでしょうが、操作手順を極限まで簡素化する工夫をしたり、タッチパネル注文のとっつきにくさを軽減する余地はもう少しありそうです。ただ、「改善のための改善」になってしまうと、見当はずれのソリューションがうまれてしまうおそれもあります。
では今度は極端な戦略として、「タブレットでのセルフオーダーを前提とし、そうでない客を完全に切り捨てる」という方針をとるのはどうでしょうか。顧客の大半が若年層の店舗の場合は一考の余地はあるかもしれませんが、今回はむしろご年配が多く訪れる店舗ですから、戦略的にも(そしてそれ以上に倫理的にも)望ましくないと考えます。むしろ正反対の「高齢者にもやさしい店」というブランディングの方が差別化要因になるやもしれませんね。
いずれにせよ、1店舗にホールスタッフが1名、という制約が最も大きいのでしょう。実際、以前の口頭で注文を受けるスタイルの頃は、ホールスタッフの方は大変忙しく動き回っていた記憶がありますが、セルフオーダー式になった今は、少し余裕ができているように見受けられました。
ーーー
あの日の店員の対応を振り返ると、おそらくはマニュアル通りではない、その場の状況に応じた柔軟な判断だったからこそ、お客さんに満足してもらえたのでしょう。システムやプロセスの最適化も当然重要ですが、そればかりを考えていると、運用する現場スタッフの心配り、という、顧客満足につながるピースを見失いかねません。
考慮すべきは、人事・組織運営の視点、社会的な観点、など、まだまだありそうですが、当然ながら、この問題に唯一の正解があるわけではありません。技術の進化、ディジタル化の波は、今後も止まることはありませんが、結局のところ大切なのは、技術導入の目的と手段を混同せず、「誰のためか」「何のためか」を常に意識し続けることなのでしょうね。間にどのような技術がはさまろうとも、人間対人間のコミュニケーションであることに変わりはないのですから。

松林 弘治 / リズマニング代表
大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期過程修了、博士後期課程中退。龍谷大学理工学部助手、レッドハット、ヴァインカーブを経て2014年12月より現職。コンサルティング、カスタムシステムの開発・構築、オープンソースに関する研究開発、書籍・原稿の執筆などを行う。Vine Linuxの開発団体Project Vine 副代表(2001年〜)。写真アプリ「インスタグラム」の日本語化に貢献。鮮文大学グローバルソフトウェア学科客員教授、株式会社アーテックの社外技術顧問を歴任。デジタルハリウッド大学院講義のゲスト講師も務める。著書に「子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい」(KADOKAWA)、「プログラミングは最強のビジネススキルである」(KADOKAWA)、「シン・デジタル教育」(かんき出版)など多数。


 【メタエンジニアの戯言】コスパとタイパは今のためならず
【メタエンジニアの戯言】コスパとタイパは今のためならず 【メタエンジニアの戯言】教育(共育)のKPIとジレンマ
【メタエンジニアの戯言】教育(共育)のKPIとジレンマ 【メタエンジニアの戯言】人間は「論理」が苦手なのか
【メタエンジニアの戯言】人間は「論理」が苦手なのか 【メタエンジニアの戯言】「ソロカル」と新技術受容
【メタエンジニアの戯言】「ソロカル」と新技術受容 【メタエンジニアの戯言】「顧客が本当に必要だったもの」2024
【メタエンジニアの戯言】「顧客が本当に必要だったもの」2024 【メタエンジニアの戯言】省略語とカタカナ用語のあれこれを考える
【メタエンジニアの戯言】省略語とカタカナ用語のあれこれを考える