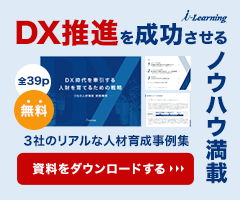アジャイルコラム:野中先生が世界に届けた “アジャイルの設計図”──そのDNAを読み解く
2025.06.27アジャイル
アジャイルには、日本の経験や知見、チーム力、組織力などが、その根底にDNAのように流れていると感じます。それは、アジャイルが欧米から入ってきた全く新しいアプローチではなく、歴史をたどれば、日本で培われた知見が海外で理論化・命名され、それが逆輸入されたものと考えてもいいのではないかと思っています。
そこで、アジャイルの祖父(Grandfather)的な存在でもあり、この分野の知識経営の権威ともいうべき野中郁次郎教授の論文に注目しました。「アジャイルソフトウェア開発宣言」や「スクラムガイド」の著者たちからも今もリスペクトされる、世界的に有名な日本人経営学者です。日本の経営学者で、ここまでグローバルで有名かつ多くの海外の専門家から認められ評価されている日本人学者は他にはそうそういないのではと思います。野中先生の経歴や功績は、多くの解説記事等でも紹介されていますのでここでは触れませんが、ネット検索すれば、アジャイル分野での野中先生の情報が沢山リストされます。ぜひ色々ググってみてください。
「The new new product development game」を読んでみた
さて、学びを深める中で、第三者の解説記事等は、お手軽で読みやすいものですが、やはりここは「1st hand information」を押さえるのが基本と考え、英語の原文を読んでみました!
The new new product development game ~ Stop running the relay race and take up rugby
タイトルに new newと重なるのは、「新しい 新製品開発」という意味ですね。要は、昨今注目されている「プロダクトマネジメント」ですが、1986年に発表されている論文です。まだ日本企業にプロジェクトマネジメントすら入っておらず、米国では、NASAが宇宙開発でプロジェクトマネジメント(ウオーターフォール)を大々的に活用していた時代です。こんな時代、1980年代は“Japan as No.1”と言われて、グローバルではソニーやキャノンなどの日本の製品が良質で高い評価と人気を博していました。そして、この日本製品の高品質はどこからくるのか、どうやって生み出されているのか、その新製品開発のカギを紐解いた論文と言われています。
さてここで、野中先生が事例として取り上げた当時の新製品を少し見てみましょう。
◆1981年 ホンダのシティ 1200cc
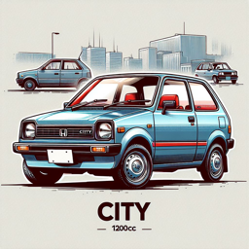
(イメージイラストはCopilotで作成)
◆1979年 NECのPC8000

(イメージイラストはCopilotで作成)
◆1979年 キャノンのオートボーイ

(イメージイラストはCopilotで作成)
昭和を生きた年代の方は、懐かしさを感じるでしょうか。上記を含む全6製品の開発の事例研究をされています。
そしてこの事例研究の中から新製品開発における6つの特長が、挙げられています。そしてこれらは、相互にダイナミックに関連していることが言及されています。(以下、原文のまま)
- Built-in instability
- Self-organizing project teams
- Overlapping development phases
- “Multilearning”
- Subtle control
- Organizational transfer of learning
今回はこの中でも、私が特に注目した”3. Overlapping development phases(オーバーラップする開発フェーズ)” について考察します。
製品開発では、ハードウェアでもソフトウエアでも、「設計→開発→テスト」といった、開発プロセスのフェーズがあるかと思います。「オーバーラップする開発フェーズ」とは、このフェーズを“重ねる“という意味です。
 当時は、ウォーターフォール型なプロジェクトマネジメントが主流の時代で、各フェーズで成果物を文書化し、それをリレーのバトンのように、分厚い文書を次のフェーズのメンバーに渡していく、そんなイメージです。
当時は、ウォーターフォール型なプロジェクトマネジメントが主流の時代で、各フェーズで成果物を文書化し、それをリレーのバトンのように、分厚い文書を次のフェーズのメンバーに渡していく、そんなイメージです。
ここで、想像してみてください。設計者と開発者とテスターは同じ人でしょうか?そうです、基本的にはフェーズごとに異なる専門家が担当しています。つまり、新製品の価値は文章という形で言語化され、いくつものフェーズを経てリレーされていくのです。
では、私たち人間はすべてを言語化できるのでしょうか?例えば、企画者や設計者の「この製品でこんなことを実現したい!これを世に出したいんだ!」という熱い想い(Passion)や構想は、十分に言語化し、次の工程に引き継ぐことができるのでしょうか?そして、その想いは最終工程まで正確に届くのでしょうか?
「伝言ゲーム」というものがありますね。人はそれぞれ異なる認知で情報を解釈します。人が異なれば理解も異なり、当然誤解も生じます。Passionや設計の背景など、言語化が難い要素はリレーされず、下流工程で、「これって何のため?」「やれって言われたからやればいいんでしょ」といった思考停止が起こる可能性もあります。
これに対し、事例として取り上げられた企業では、各フェーズを重ねることにより、情報の分断や誤解を最少化しているというものです。また、関連するポイントとして、設計者もその想いを実現するために最後まで参画したり、テスターも企画や設計段階から関与し、意図や想いを理解してOne Teamで1つの新製品開発に取り組む、という構図です。
これは、まさにラグビーのイメージです。1つのゴールを目指 して全員でフィールドを縦横無尽に駆け巡り、後ろにパスをつなぎながら、ディフェンスに阻まれても何度も立ち上がる。スクラムで力を1点に集中して、壁を突破する。プレイヤーひとりひとりの判断や想いが、チームとしてつながり、ブレイクスルーを生み出すのです。この考え方は “2. Self-organizing project teams” にも大きく関連しています。いわゆる「自己組織化」、すなわち「自律的な組織」、「自律的な人材」が重要です。これこそが、実はスクラムの重要な要素です。
して全員でフィールドを縦横無尽に駆け巡り、後ろにパスをつなぎながら、ディフェンスに阻まれても何度も立ち上がる。スクラムで力を1点に集中して、壁を突破する。プレイヤーひとりひとりの判断や想いが、チームとしてつながり、ブレイクスルーを生み出すのです。この考え方は “2. Self-organizing project teams” にも大きく関連しています。いわゆる「自己組織化」、すなわち「自律的な組織」、「自律的な人材」が重要です。これこそが、実はスクラムの重要な要素です。
もちろん、ウォーターフォール的なプロジェクトマネジメントは、現在も主流でありその有効性は周知の事実です。一方で、変化の速い現在においては、変化に俊敏に適応するアプローチとして「アジャイル」が注目されているのです。つまり使い分けがポイントなのです。
さて、今回は、アジャイルの伝説の論文の一部をピックアップして、考察してみました。そして、この論文に“ラグビーのスクラム”が言及されています。これこそ、今のアジャイルの代表的な実践形態である「スクラム」という名称の発祥の論文です。そういう意味で、野中先生こそ、まさにスクラムのGrandfatherではないでしょうか。
アジャイルのDNA、これは野中先生の論文、「スクラム」の語源(生みの親)、つまり日本にアリ!です。
<執筆後記>
私は、野中先生の提唱された「SECIモデル(*1)」の大ファンで、この論文を参考文献としてプロジェクトマネジメントの論文を書いたこともあります。暗黙知を形式知にすることは、今もなお永遠のテーマではないでしょうか。野中先生には、常々リアルで講演等でもお会いしたいと思っていました。そんな中、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、大変悲しいことに、2025年1月26日に逝去されました。アジャイルの巨匠の多くの方々が哀悼メッセージを各所で発表されています。私も心より哀悼の意を表したいと思います。
*1:(Wikipediaより)SECIモデル

阿部 仁美 / 株式会社アイ・ラーニング
研修企画開発プロデューサー(専門分野:アジャイル&プロジェクトマネジメント)
Certified Scrum Master (CSM)®、Registered Scrum Master (RSM)®、Project Management Professional (PMP)®
日本アイ・ビー・エム株式会社にて、SW新製品開発/ITシステム開発のプロジェクト・マネジャー、プロジェクト・レビュー、および日本アイ・ビー・エム社全体のプロジェクト・マネジャーの育成・認定等に30年以上従事。情報処理推進機構(IPA)にて人材育成に携わった後、楽天モバイル株式会社にてPMO:新製品開発プロセス策定/強化に取り組む。2022年より現職。DXの構造における①ベンダー企業②官③事業会社の3つの視点の業務を経験。