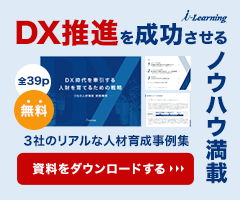新人エンジニアに求められる学び続ける力と論理的思考力 〜インプル社が語るAI時代に必要なスキル〜
2025.03.03お役立ち情報
■株式会社インプル 代表取締役CEO (左から2番目)
西嶋 裕二
■株式会社インプル コーポレートグループ・HRチーム (左から3番目)
川端 翔平
普段はシステム開発プロジェクトに参画し、主にウェブアプリケーションやモバイルアプリの開発を担当。現在はプロジェクトマネージャーも担当。アイ・ラーニングの新入社員研修ではメイン講師・サブ講師も含め5年ほど務める。
■株式会社インプル コーポレートグループ・HRチーム (1番右)
松尾 統子
保守チームのマネージャー。モバイル系のアプリケーション保守のほか、広くシステム保守の案件を担当。アイ・ラーニングの新入社員研修ではメイン講師・サブ講師も含め5年ほど務める。
■聞き手:
株式会社アイ・ラーニング 代表取締役社長 (1番左)
杉山 真理子
今回は、アイ・ラーニングの新入社員研修で講師を務めるパートナー企業、インプル社に取材しました。アプリ開発の最前線でも活躍する講師陣に、現代の新人エンジニアに求められるスキルや育成方法について、具体的な現場の視点からお話を伺いました。
スマホ黎明期に誕生したインプル社
2011年、スマートフォンの普及が始まった黎明期に、インプル社は北海道札幌で創業しました。同社はスマホアプリ開発に特化した事業を軸に成長を続けています。創業当時を振り返り、西嶋社長はこう語ります。
「ちょうどiPhone4が出た頃、アプリ開発は主に個人の開発者がゲームを開発されていましたが、当時、ビジネスユースはそれほど事例がありませんでした。そこで、お客様からスマホのアプリでこういうことができないかというご相談を多くいただいたところから、私たちはビジネス用途でも広がると感じて事業をスタートしました。」
 西嶋社長は、地元札幌の「サッポロバレー」(札幌のベンチャー企業群)で20代を過ごし、自由で風通しの良い企業文化や、成長し続ける組織の挑戦する姿勢に深い影響を受けてきました。この経験をもとに、『次世代を実装する』」というビジョンを掲げ、教育をはじめ社会に貢献する取り組みを続けています。
西嶋社長は、地元札幌の「サッポロバレー」(札幌のベンチャー企業群)で20代を過ごし、自由で風通しの良い企業文化や、成長し続ける組織の挑戦する姿勢に深い影響を受けてきました。この経験をもとに、『次世代を実装する』」というビジョンを掲げ、教育をはじめ社会に貢献する取り組みを続けています。
アイ・ラーニングとは2015年頃に出会い、西嶋社長はアイ・ラーニングの新入社員研修の講師を担当。「若い世代に教えることで多くの学びを得られるのではないかと考え始めました。講師を務めることで、普段は要件に合わせて限られた範囲にとどまりがちな学びが、より広がりを持つと感じたからです。また、教えること自体が講師の学びや成長にもつながると考え、それ以来約10年間にわたり、アイ・ラーニングに数多くの講師を派遣し続けています。」
新入社員に求められる『学び方』の習得
『学び方』を教える教育の意義
インプル社の講師がアイ・ラーニング社のお客様向けに提供するエンジニア向け新入社員研修では、技術そのものを教えるだけでなく、『学び方』を身につけることに重きを置いています。これは、技術やツールが日々進化する現代において、持続的に成長し続けるための力を育むためです。
「技術を学ぶことはもちろん重要ですが、繰り返しやっていく中で推測の能力や精度をどんどん上げていき、引き出しを増やしていくことが大切です。そうすることで、後々別の問題にぶち当たった時の問題解決能力が向上します。」と松尾講師は語ります。
『学び方』というのを最初に身につけてあげることが重 要で、新入社員の方々に良質の学びの型を作ってあげられると、その後の成長につながります。研修では、教材や課題を通じて、自ら情報を調べ、試行錯誤しながら解決策を見つけるプロセスが組み込まれています。講師陣は受講者に寄り添いながら、「答えを教える」のではなく、「答えを導き出す力」を引き出す工夫をしています。
要で、新入社員の方々に良質の学びの型を作ってあげられると、その後の成長につながります。研修では、教材や課題を通じて、自ら情報を調べ、試行錯誤しながら解決策を見つけるプロセスが組み込まれています。講師陣は受講者に寄り添いながら、「答えを教える」のではなく、「答えを導き出す力」を引き出す工夫をしています。
『学び方』の応用範囲
学びの基礎が身につくと、新しい技術や知識を効率的に習得するだけでなく、それを幅広い場面で応用できるようになります。プログラミング研修を通じて『学び方』を習得することで、受講者の成長を加速させることができます。
「プログラミングの学習で培った『学び方』は、他の技術分野においても非常に役立ちます。特にJavaは開発環境自体から学ばなければいけないし、言語仕様が複雑なので、学ぶことが深くて広範囲です。そういった意味で、学習時間もすごくかかるのですが、難易度の高いものを最初に新人でやるというのは、本人にとっても自信がつき、他の言語の習得も容易になります。」
「振り返ってみると、自分自身もJavaを学べたことがすべての土台になっています。基礎的な知識はJavaで培って、あとは言語によって特徴的なところを吸収できれば応用がきくかと思います。」(西嶋社長・川端講師)
受講者が自ら問題を特定し、適切な解決策を導き出す力を得られるようになってくれば、プログラミングだけでなく、プロジェクトやチームでの業務にも応用できるようになっていきます。
「継続的な成長」を可能にする仕組み
自ら学び続ける力の育成
新入社員にとって、学び続ける力を身につけることは、キャリアを通じて成功するための鍵となります。研修では、研修終了後も自ら成長し続けられるよう、学びの土台を築くことを目指しています。
 「技術は絶えず変化しているので、まずは自分自身で技術トレンドや自分が得意な技術領域でもいいので、自身でキャッチアップする姿勢が必要だと思っています。」
「技術は絶えず変化しているので、まずは自分自身で技術トレンドや自分が得意な技術領域でもいいので、自身でキャッチアップする姿勢が必要だと思っています。」
「常に学び続けること。技術という面で新しい情報を取り入れ続けるところ、調べ続けることが定着につながります。」と西嶋社長、川端講師は言います。
受講者は研修中に、自ら調べる力を鍛えるだけでなく、得た知識をどう応用するかも学びます。これにより、技術トレンドが変化しても、常に自分をアップデートし続けることが可能になります。
また、継続的な成長を支えるもう一つの要素は、“挫折を乗り越える経験”です。研修では、受講者が自分で解決しなければならない課題が多く与えられます。自ら解決していくことにより、「解決に至るまでのプロセスを楽しむ力」が養われます。
コミュニケーション力の育成:学びを広げるための基盤
チーム内での協働がもたらすコミュニケーション力
新入社員が社会に出て直面する最大の課題の一つが、職場での効果的なコミュニケーションの取り方です。研修では、技術の習得に加え、コミュニケーション力の向上にも重点を置いています。
 「今の新入社員は、コロナ禍で大学に通わずオンラインに慣れている世代でもあります。アルバイトも含めてリアル経験が少なく、人と会話する機会が不足し、質問の仕方が分からないなどの課題があります。そのため、研修ではグループワークなどコミュニケーション力を育む仕掛けを取り入れています。」と松尾講師は説明します。
「今の新入社員は、コロナ禍で大学に通わずオンラインに慣れている世代でもあります。アルバイトも含めてリアル経験が少なく、人と会話する機会が不足し、質問の仕方が分からないなどの課題があります。そのため、研修ではグループワークなどコミュニケーション力を育む仕掛けを取り入れています。」と松尾講師は説明します。
優れた技術力を持っていても、それを適切に伝えたり、チームで協働する力がなければ成果を上げることは困難です。グループワークや演習といったチームでの取り組みを通じて、受講者が自然に他者と意見を交わしながら学ぶ環境を用意することで、受講者は自分の考えを言葉で整理し、相手にわかりやすく伝える力を養います。
コミュニケーションの課題に応じたアプローチ
近年、オンライン授業やリモート学習の影響で、対面でのコミュニケーション経験が不足している新入社員が増えています。このような状況に対応するため、研修プログラムではまず「話しやすい雰囲気づくり」から始めることを重視しています。
「受講者同士がリラックスして話せるように、技術の前にまず関係性をつくることが重要です。グループワークを主として、会話をする機会を設定します。コミュニケーションができるとお互いちょっと安心して、自然と相談や意見交換もしやすくなります。」と松尾講師は語ります。
研修中には、仮想プロジェクトの形式で、チームごとにタスクを分担しながら課題を解決する演習が行われます。講師は技術面とは違う気遣いや気持ちの汲み取りを大切にすることで、受講者は「自分の役割を果たすだけでなく、他者と連携しながら目標を達成する力」を身につけていきます。
論理思考力とAI時代の教育
論理思考力の重要性:基礎力としての役割
 論理思考力は、AI時代においても揺るぎない基礎力として重要な位置を占めています。AIや高度なツールがどれほど進化しても、それを適切に活用するためには、人間が問題を正しく理解し、論理的に解決する力が不可欠です。
論理思考力は、AI時代においても揺るぎない基礎力として重要な位置を占めています。AIや高度なツールがどれほど進化しても、それを適切に活用するためには、人間が問題を正しく理解し、論理的に解決する力が不可欠です。
「古くはパソコンを使える世代とそうじゃない世代のように、今ではAIを使えるかどうかで格差ができてしまいます。今の新入社員はAIをキャッチアップしないと、ググれない人と一緒の状態になってしまいます。これはエンジニアに限らず、すべての人が身につける必要があります。」と西嶋社長は語ります。
AIと人間の協働における論理思考の役割
AIが普及することで、人間とAIの協働が求められる時代が到来しています。ここで重要なのは、AIの能力を補完する形で人間が論理思考力を発揮することです。
「プロンプトエンジニアリングでは、結局、対人間でコミュニケーションを取れない人はAIもうまく使えないと言われています。どういうインプットをするかが重要で、技術的な知識だけでなく、生成結果を検証するための思考力や、適切なリクエストを伝えるコミュニケーション能力の要素が必要とされていくと思います。
一例ですが、全くプログラミングを自分でしたことのない人がAIにコードを書かせてうまくいくかというと、90%ぐらいはうまくいきます。残りの10%ですが、自分でこれが合っているかどうかの確認は人がやらないといけません。結局、エンジニアの経験がある人の方が、早く正解にたどり着けるのです。
今まではコンピュータに合わせて機械がわかるプログラミング言語を人間が身につけていましたが、今後は、それ以前に人間が“人間の言葉”でちゃんと何が欲しいかということを記述できることが重要となります。」と西嶋社長は述べます。
AIはあくまで「道具」であり、その活用方法を決めるのは人間の判断力です。AIを効果的に使いこなすには、単に技術力を高めるだけでなく、適切なリクエストをまとめる力の両方が求められていきます。これらは、これからの時代に求められる重要な力となっていくはずです。
インプル社が描く教育の未来
技術教育を超えた「人間力」の育成
インプル社は、スマホアプリ開発にとどまらず、北海道の非ITの事業会社向けにDX支援やデジタル化の支援も行なっています。さらに、一般財団法人などと共催でXR技術のイベントを開催するなど、常に技術の先端を牽引しながら、社会貢献にも力を注いでいます。その豊富な知見やノウハウ、そして現場で培われたマインドなどを持つ技術者がアイ・ラーニングの講師を務めることで、単なる技術教育にとどまらず、受講者が社会で活躍するために必要な「人間力」の育成にも重点を置いています。
急速に変化する現代社会において、受講者が柔軟に自立して対応できるようになることを目指し、『次世代を実装する』 というビジョンを掲げるインプル社と、『実装人材を育成する』 ことを目指すアイ・ラーニングがタックを組むことで、技術力だけでなく、社会的なスキルや適応力、応用力を育む教育を実現しています。
両者は、単なるビジネス上の協力関係を超え、「教育を通じて社会をより良くする」という共通のビジョンにのもと、今後もより多くの受講者に質の高い教育をご提供し続けます。

西嶋社長が着ているのはインプル社オリジナルのパーカー。経営合宿などでは全員が着るという。
■インプル社について
https://www.imple.co.jp
- 拠点:札幌本社、東京オフィス
- 創業:2011年6月
- 社員数:約170名
- ビジョン:「IMPLEMENT NEXT GENERATION(次世代を実装する)」
- 企業理念:「先進技術で革命を起こす」
- 事業内容:スマホアプリ開発、Webシステム開発、ブロックチェーン技術を使ったNFTエコシステム構築、 システムインテグレーション事業
エンジニア育成や新入社員育成など、育成に関するお悩みや課題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
・お問い合わせフォーム
https://www.i-learning.jp/contact/
お客様のご要望や課題にあわせた、1社専用研修のご用意もございます。
・プライベート研修
https://www.i-learning.jp/service/private-training/


 メンバーを牽引するチームリーダーの役割とは?
メンバーを牽引するチームリーダーの役割とは? Society 5.0/第四次産業革命とは?実現のために必要なこと
Society 5.0/第四次産業革命とは?実現のために必要なこと マネジメントの聴く力・伝える力を変えるフィードバックとは
マネジメントの聴く力・伝える力を変えるフィードバックとは 自社のITリテラシーに不安を持つDX人材育成担当者に捧げる~失敗しないDX人材育成 虎の巻~
自社のITリテラシーに不安を持つDX人材育成担当者に捧げる~失敗しないDX人材育成 虎の巻~ 「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~実践企業の事例から紐解くカスタマーサクセスの最前線
「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~実践企業の事例から紐解くカスタマーサクセスの最前線 未来にワクワクする働き方とは? 〜 変化の時代の人づくり、「活学」は学ぶ心のスイッチ〜
未来にワクワクする働き方とは? 〜 変化の時代の人づくり、「活学」は学ぶ心のスイッチ〜