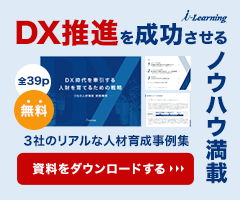【メタエンジニアの戯言】DM文化と公開チャンネル文化は対立項か
2025.10.06松林弘治の連載コラム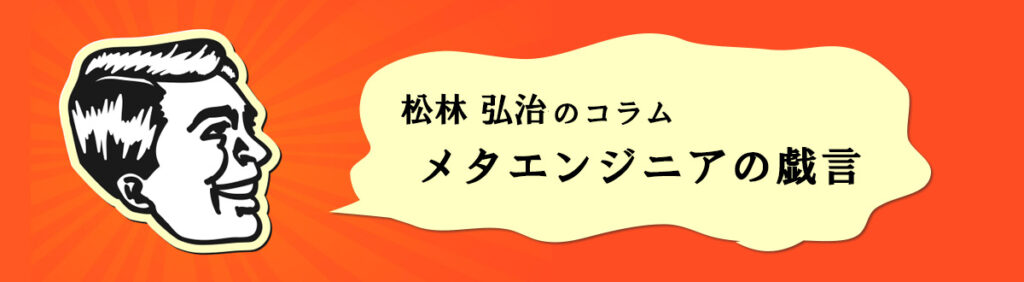
対面での会話、手紙、電話、ファクス、電子メールなど、ビジネスコミュニケーションの形はさまざまですが、近年は社内のやり取りに Slack や Microsoft Teams を使う職場が増えました。一般論として、Slack はエンジニア組織で、Teams は Office 連携を重視する部門で選ばれやすい傾向があるようです(もちろん例外もあります)。
こうしたツールは今や一般的ですが、職場や業種、組織構造によって使われ方は驚くほど異なります。その中でも、よく耳にする典型的な意見の相違が「DM派 vs 公開チャンネル派」です。
ーーー
公開チャンネル派、すなわちDM否定派の言い分は例えばこんな感じでしょう。
「DMでのやりとりばかりだと、いつ・誰が・何を決めたのか、が曖昧になり、把握すべき人に情報が届かないまま進行しがち」
「会話が散らばり、あとから経緯を追うのが難しくなる、ましてやDMやプライベートチャンネルだと、参加者以外が参照できない」
「WIP(Work in Progress:現在進行中)の段階であっても、その過程を発言というログにしておくことで、あとで文脈が追いやすくなるのに、DMではそれができない」
「DM依頼はタスクを属人化させやすく、作業が不透明になりやすい」
「DMは、電話や対面での会話のように相手の時間を奪いやすい同期的な使い方になりがちで、非同期コミュニケーションの利点(待てる・検索できる・割り込みが少ない)を損ねやすい」
一方、DM派の意見はこんな感じでしょうか。
「特に参加人数の多い場では、発言がより多くの人の目に晒されることになり、発言の心理的コストが大きくなりやすいし、発言意欲が落ちてしまいがち」
「なんでもかんでも公開チャンネル上で会話をしていると、あとで検索するのが大変になるのではと感じる」
「DMならば、電話や対面のように粗く気軽に相談しやすく、気まずさもない、結果としてより活発に同期的コミュニケーションが生まれる」
「個人情報や対外非公開情報などを公開チャンネルで書くのはそぐわないため、DMなどの限定共有がふさわしい」
私自身の考えは、かなり公開チャンネル派寄りですが(笑)、かといって「DMでのコミュニケーションは禁止」とまでは思っていません。問題は「どちらが正しいか」ではなく、使い分けの設計にあると考えています。皆さんはどのように感じられますでしょうか。
ーーー
当然のことですが、「公開チャンネルでの議論」と「DMやプライベートチャンネルでの会話」とは、対立項では決してありません。どちらにもメリット・デメリットがあり、互いの良さを生かすようにコミュニケーション設計をすべきだ、というのが現実的な落とし所と考えられます。
あくまで一例ですが、次のように整理することができるでしょう。
- DMはあくまで作業用チャンネルと意識
- 法務やセキュリティなどデリケートな話題、個人的な相談はDMや限定共有
- 皆に伝えたい知見や、決定・共有事項は公開チャンネル(適切なチャンネルを選ぶ)
- 全体展開する前の1on1的なブレストは場合によってはDMも可、ただしそこでの合意や決定は公開チャンネルに要約を還流
- 多くの人の意見や知見を集めたい相談は、ドラフトであっても公開チャンネル上で(ただし話題に応じたチャンネルの使い分け、スレッド使用、タグ付け、などで識別しやすく)
- 心理的安全性を確保しつつ発言しやすいよう、公開チャンネルに慣れている人が未完成でも出してよいというスタンスでサンプル発言を示すなど、敷居をさげる
ーーー
結局のところ、最適解は「どのような組織、どのような関係性、どのような業務」かに依存してしまうでしょう。ただ、せっかくのコミュニケーションツール導入によって風通しがより悪くなってしまわないよう、「小部屋(DM)で素早く不安を解消したりすり合わせたり煮詰めたりする」、そこから「広間(公開チャンネル)で議論や学びを資産化し共有する」という往復の意識は、最初に合意しておきたいところです。
一方で、プロジェクト初期は非常にタイトな意思疎通と迅速な意思決定ができていたのに、参画メンバが増えるにつれ徐々にDM偏重へと傾いていくケースもいくつか目にしてきました。人数増加により、心理的コストが増えやすく、ノイズへの懸念も増しやすいからなのでしょう。
全員が「木」つまり枝葉末節まで把握している必要はありませんが、「森」つまり全体のビジョンや個々の関係性や役割を共有し、記録や知見を残していってこそ、齟齬は減り、大きなチームでの見通しが良くなっていくはずです。
…などと全体設計・運用に思いをめぐらせつつ、いまだにしっくりこない Teams の使い勝手に困惑しているのでした。

松林 弘治 / リズマニング代表
大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期過程修了、博士後期課程中退。龍谷大学理工学部助手、レッドハット、ヴァインカーブを経て2014年12月より現職。コンサルティング、カスタムシステムの開発・構築、オープンソースに関する研究開発、書籍・原稿の執筆などを行う。Vine Linuxの開発団体Project Vine 副代表(2001年〜)。写真アプリ「インスタグラム」の日本語化に貢献。鮮文大学グローバルソフトウェア学科客員教授、株式会社アーテックの社外技術顧問を歴任。デジタルハリウッド大学院講義のゲスト講師も務める。著書に「子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい」(KADOKAWA)、「プログラミングは最強のビジネススキルである」(KADOKAWA)、「シン・デジタル教育」(かんき出版)など多数。


 【メタエンジニアの戯言】教育(共育)のKPIとジレンマ
【メタエンジニアの戯言】教育(共育)のKPIとジレンマ 【メタエンジニアの戯言】良い組織を維持し変わり続けることの難しさ
【メタエンジニアの戯言】良い組織を維持し変わり続けることの難しさ 【メタエンジニアの戯言】人間は「論理」が苦手なのか
【メタエンジニアの戯言】人間は「論理」が苦手なのか 【メタエンジニアの戯言】「ソロカル」と新技術受容
【メタエンジニアの戯言】「ソロカル」と新技術受容 【メタエンジニアの戯言】「顧客が本当に必要だったもの」2024
【メタエンジニアの戯言】「顧客が本当に必要だったもの」2024 【メタエンジニアの戯言】「『新しい』への懸念」は本当に新しいのか
【メタエンジニアの戯言】「『新しい』への懸念」は本当に新しいのか