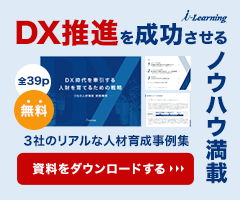【メタエンジニアの戯言】「20kHz神話」と部門間コミュニケーション
2025.07.07松林弘治の連載コラム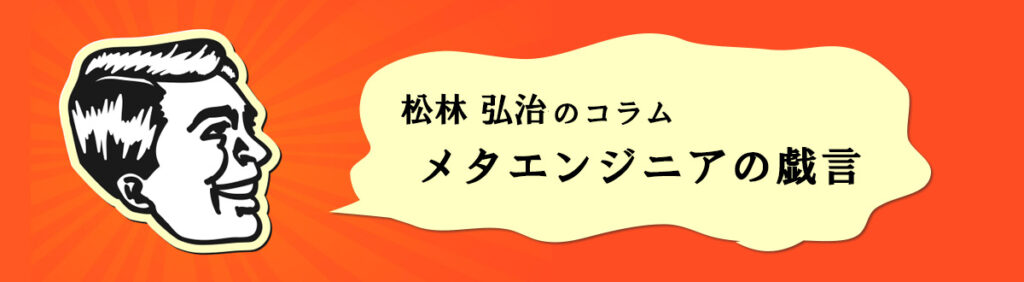
半年ほど前に知り合って以来、懇意にさせていただいている、一回り以上先輩の知人がいます。ジャズやブルース、ソウルなどをアナログレコードで愛聴されている方です。
この方は「レコードには20kHzを超える音が入っているからCDより高音質だ」「初出のオリジナル盤こそ至高だ」と強く信じておられました。私もレコード蒐集・再生を愛好していますが、同時にディジタルの忠実度や再現性も高く評価しています。アナログとディジタル、それぞれの仕組みや技術史を学べば学ぶほど、両者の技術の素晴らしさに心を打たれます。
私としては「20kHz神話」や「オリジナル盤至上主義」は科学的・技術的に必ずしも正しいとは言えない、と思っていますが、そのことを知人にどうやって伝えたものか、少々悩みました。当然ながら、一方的に正論をぶつけたところで思いは伝わりませんし、そもそも論破したいわけではありません。
ーーー
ビジネスの現場でも似たような状況に遭遇することがあるでしょう。例えば、開発部は機能優先、営業部は納期優先、経理はコスト優先、など。それぞれが「自分たちの正義」を振りかざしてしまうと、議論は平行線をたどりがちです。
システム開発現場でも、プロジェクトマネージャ、テックリード、エンジニアの間、あるいはバックエンド担当、フロントエンド担当、DB担当、テスト担当、保守運用担当などの間、など立場が交差する際に衝突が起こることがあります。技術的に優劣がつけにくい、個々の信念やポリシーに関わる内容ならなおさらです。
ーーー
閑話休題。今回はあくまで趣味での話ですので、そこま で深刻に考える必要はないのかもしれません。ですが、音楽やオーディオに対する思い入れや信念の強さは時に宗教論争の様相を呈することもある(笑)ため、今回は各種開発プロジェクトの時のことを思い出したりしながら、どのような対話が可能か知恵を絞ってみました。
で深刻に考える必要はないのかもしれません。ですが、音楽やオーディオに対する思い入れや信念の強さは時に宗教論争の様相を呈することもある(笑)ため、今回は各種開発プロジェクトの時のことを思い出したりしながら、どのような対話が可能か知恵を絞ってみました。
ビジネス用語っぽく言うと、「アクティブリスニング」「NVC(非暴力コミュニケーション)」「心理的安全性」「ダブルループ学習」「イシューとポジションとインタレストの分離」などでしょうか。これらを専門的に学んだことはありませんが(笑)、いずれも自分が日常生活現場でも教育現場でも気を付けていることに近いものといえます。
ーーー
さて後日、知人宅を訪問する機会がありました。ご自慢のシステムで至極のコレクションを解説付きで堪能させていただいたあと、持参していった古いDAC(ディジタル=アナログ変換装置)とノートPCを知人のシステムに接続させてもらい、知人の好きな音楽をいろんな音源で一緒に聴いてみました。その合間に、技術的な仕組みや歴史についても平易にお伝えしました。
すると意外なことに、知人は強く興味を示した上で、「ディジタルに対する今までの思い込みを改める必要があるかもしれない」「レコード再生時のわずかな歪みによって、心地よく聴こえている可能性もありそうだ」「依然レコード再生の方が好みだが、自分もDACを導入してみたくなった」と、概ね好意的な反応でした。私も、知人にとってアナログ再生のどういったところが琴線に触れるのか、その気持ちが理解できた気がしました。
ーーー
今回の場合は、議論の工夫によりうまい具合に着地できた、というよりは、むしろ好奇心旺盛な知人の懐の深さに助けられた面が大きかったのかもしれません。それでも、それぞれの主張のぶつけ合いではなく、違いの興味や嗜好を認めあい、事実と解釈を切り分けながら議論を重ねたことで、話が広がり深まっていく過程は、非常に有意義なものでした。
一方、ビジネスの現場においては、個々人の度量に頼ることができませんから、本稿中盤で触れたようなキーワードを仕組みとして導入する必要があるでしょう。
知人とレコードを聴きつつ音楽談義をしながら、そんなことまで脳裏を巡った、そんな楽しいひとときでした。

松林 弘治 / リズマニング代表
大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期過程修了、博士後期課程中退。龍谷大学理工学部助手、レッドハット、ヴァインカーブを経て2014年12月より現職。コンサルティング、カスタムシステムの開発・構築、オープンソースに関する研究開発、書籍・原稿の執筆などを行う。Vine Linuxの開発団体Project Vine 副代表(2001年〜)。写真アプリ「インスタグラム」の日本語化に貢献。鮮文大学グローバルソフトウェア学科客員教授、株式会社アーテックの社外技術顧問を歴任。デジタルハリウッド大学院講義のゲスト講師も務める。著書に「子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい」(KADOKAWA)、「プログラミングは最強のビジネススキルである」(KADOKAWA)、「シン・デジタル教育」(かんき出版)など多数。


 【メタエンジニアの戯言】教育(共育)のKPIとジレンマ
【メタエンジニアの戯言】教育(共育)のKPIとジレンマ 【メタエンジニアの戯言】良い組織を維持し変わり続けることの難しさ
【メタエンジニアの戯言】良い組織を維持し変わり続けることの難しさ 【メタエンジニアの戯言】人間は「論理」が苦手なのか
【メタエンジニアの戯言】人間は「論理」が苦手なのか 【メタエンジニアの戯言】「ソロカル」と新技術受容
【メタエンジニアの戯言】「ソロカル」と新技術受容 【メタエンジニアの戯言】「顧客が本当に必要だったもの」2024
【メタエンジニアの戯言】「顧客が本当に必要だったもの」2024 【メタエンジニアの戯言】「『新しい』への懸念」は本当に新しいのか
【メタエンジニアの戯言】「『新しい』への懸念」は本当に新しいのか