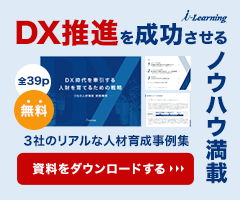未来にワクワクする働き方とは? 〜 変化の時代の人づくり、「活学」は学ぶ心のスイッチ〜
2025.09.30お役立ち情報
私たちは今、人口減少と価値観の多様化によって、成長社会から成熟社会へと移行しました。もはや画一的な幸福のモデルは存在せず、一人ひとりが自らの意味と方向性を探す時代に生きています。 この不確実で複雑な環境をどう生き抜き、未来に活力を見いだすか。その答えのヒントとなるものが、人間の根源的な力に光を当てた「活学」です。

並木 将央 氏
株式会社ロードフロンティア 代表取締役社長
中小企業診断士、MBA(経営管理修士)、電気工学修士 マスタービジネスコンサルタント(日本コンサルタント協会認定)、ITコーディネータ(経済産業省推進資格)、AI・IoTシニアコンサルタント(AI・IoT普及推進協会認定)、大学講師
半導体メーカー研究開発を経て独立。新規事業開発、企業再生、IT導入、WEB、戦略などのコンサルティングまで広範に事業展開中。地方行政機関を含め、業種形態を問わずコンサルティングを行う。2014年「The Japan Times」の選ぶ「次世代を担うアジアの経営者100人」に選ばれる。
成熟社会~VUCAの時代~における働き方の転換
日本は長らく人口増加を背景に「成長社会」を歩んできました。しかし2008年を境に人口は減少へ転じ、「成熟社会」に入りました。モノやサービスがあふれ、人々の価値観は多様化。従来のように「豊かな暮らし=幸せ」という単一の尺度だけでは、生きる活力を持ちにくい時代になっています。
この社会的背景は、働き方や生き方の在り方を根本から見直す契機となっています。
成熟社会を特徴づける概念が VUCA です。
- Volatility(変動性)
- Uncertainty(不確実性)
- Complexity(複雑性)
- Ambiguity(曖昧性)
かつての社会は「不足や不便」を解消することで成長してきました。しかし現代は、モノ・サービス・情報の過剰によって、次に起こることを正確に予測できない時代となっています。 このVUCAの時代には、「指示待ち」ではなく、自ら考え、選び、行動できる主体性こそが求められます。
活学
活学とは

「活学」とは、心理学・社会学・物理学・哲学の知見から「活力」に関する部分を抽出し再構成した、並木氏によるオリジナルの学問です。
人が前向きに生きるためのエネルギー=「活力」をどう育み、どう活かすかに特化している点が特徴です。
かつて哲学者・安岡正篤氏も「活學」という言葉を用いましたが、並木氏の活学は現代社会における働き方・生き方に直結する「学びのスイッチ」として体系化されています。
活力の有無が生き方を左右する
活力の有無は、成果や成長に直結します。
- 活力のある人は、目標に向かって柔軟に行動し、困難を乗り越えていける。
- 活力のない人は、受け身に陥りやすく、自分の存在意義を見失いがちになる。

心理学では「生きる意味がわからない」状態を「実存的空虚感」と呼びます。活学ではさらに「活力のなさ」を加え、「実存的虚無感」と表現しています。これは、現代社会を生きる多くの人に共通する課題ともいえるでしょう。
活力のセルフチェック
自身の状態を客観的に把握するうえで、「いま自分に活力があるかどうか」を確認することは重要です。定期的にセルフチェックを行い、自身の活力の状態に気づくことが、継続的なパフォーマンスの維持や、コンディション調整につながります。

魂魄(こんぱく)

活力を高めるために欠かせないのが「魂魄(こんぱく)」の存在です。
- 魄:本能的な感情や身体的な働き、生まれ持った力
- 魂:その魄に方向性を与え、心を成長させる力
魂と魄が結びついたとき、人は生命力や判断力を備え、逆境を乗り越える力を発揮します。逆に魂魄が弱い人は心が折れやすく、持続的な成果を出すことが困難になります。
現代の成熟社会では、この魂魄が弱まり「生きる力」そのものが落ちている人が増えています。だからこそ、意識的に育んでいくことが求められるのです。
魂魄が育ってる人
魂魄がしっかりと育っている人は、自分の「軸」をもっています。
- 困難や逆境に直面しても、感情に振り回されず、自らの価値観に基づいて判断できる。
- 目標に向かって粘り強く努力を続け、成果を積み重ねることができる。
- 他者の意見を取り入れながらも、自分の判断に責任を持ち、主体的に行動できる。
こうした人は、組織の中で自然にリーダーシップを発揮し、周囲にも前向きな影響を与えます。
魂魄が育っていない人
一方、魂魄が十分に育っていない人は、外部の状況や他者の評価に過度に依存しがちです。
- 逆境に弱く、困難に直面すると心が折れやすい。
- 判断軸を持たず、指示がなければ動けない。
- 周囲に流されやすく、自分の存在意義を見失いやすい。
その結果、持続的な成果を出しにくく、リーダーとして組織を引っ張る力も発揮できません。
成長社会の時代には、魂魄を持つ人が多く存在しました。豊かさを求め、皆が前向きに努力していたからです。社会の秩序を守り、相手を思いやることが自然と浸透し、それが活力の源になっていました。
しかし、成熟社会に入った現在は、魂魄が弱まり「生きる力そのものが落ちてきている人」が増えています。それにもかかわらず、昔の価値観のまま「人に気を遣いなさい」と言い続けると、自分自身の心がすり減り、「何のために生きているのか」が見えなくなってしまいます。この状態こそが、活学でいう「実存的虚無感」を生み出す要因です。
自分らしい働き方を描くために

成熟社会には「決まった幸せの道」はありません。だからこそ、自分自身の ビジョン を持つことが不可欠です。 ビジョンとは「自分はどう生きていたいか」という“状態”を描くもの。自らの価値観を明確にし、それを土台にして生き方や働き方を選ぶことで、人は再び活力を取り戻せます。
活力にあふれる組織の作り方
成熟社会において組織が活力を維持し続けるためには、単に制度や仕組みを整えるだけでは不十分です。人の心や感情に根ざした「エネルギーの源泉」をどう引き出すかが鍵となります。

組織が活力を持ち、社員が意欲的に働けるためには、以下の6つの条件がバランスよく満たされていることが不可欠です。 これらの条件のうち、特に報酬・職場環境・やりがいの三要素が欠けると、社員の期待値は下がり、組織への信頼や貢献意欲が失われていきます。欠如が長期化すると、社員は「会社に期待しない」姿勢になり、組織の活力は急速に低下します。
逆に、これら6つの条件がバランスよく満たされていると、社員は心を開き、エネルギーを外に向けて発揮し、組織全体が活性化していきます。
感情のマネジメント
AIが台頭する時代であっても、働く主体はあくまで人間です。 だからこそ、経営やマネジメントにおいて重要なのは「感情の管理」です。
数値やKPIだけで人を動かそうとするのではなく、メンバー一人一人の不安や不満、喜びや誇りといった感情をどう扱うか、そこに寄り添えるかどうかが、リーダーの資質を決定づけます。
社員の感情に無関心なリーダーのもとでは、組織の活力は決して育ちません。
リーダーに求められる姿勢
活力にあふれる組織を生み出すには、リーダーが「人に興味を持ち、感情に寄り添える存在」であることが不可欠です。最低条件は以下の3つです。
- 自社を愛すること
- 自分自身をよく理解していること
- 自社を誇りをもって語れること
逆に、人に無関心な人物をリーダーに据えてはいけません。組織の方向性や戦略がいかに優れていても、リーダーが人の心に興味がなければ、共感も生まれず、活力も生まれないからです。
自己実現を支援する企業へ
 成長社会では、会社が掲げるビジョンに社員を従わせることができました。しかし成熟社会では、社員一人ひとりが異なるビジョンを持っています。そのため、企業は社員のビジョンを応援し、自己実現を支援できる存在でなければなりません。 社員が「ここなら自分の人生を活かせる」と感じたとき、組織は初めて「活力にあふれる場」となります。
成長社会では、会社が掲げるビジョンに社員を従わせることができました。しかし成熟社会では、社員一人ひとりが異なるビジョンを持っています。そのため、企業は社員のビジョンを応援し、自己実現を支援できる存在でなければなりません。 社員が「ここなら自分の人生を活かせる」と感じたとき、組織は初めて「活力にあふれる場」となります。
最後に
“未来にワクワクする働き方”を実現するには、社員一人ひとりが自分のビジョンに向かって、活力を持って歩み出すことが不可欠です。そして、企業はその自己実現を支援し、共に未来を描く存在であるべきです。 活学は、この変化の時代における「学びのスイッチ」として、私たちが生きる力を取り戻し、未来を切り拓くための指針を与えてくれます。


 メンバーを牽引するチームリーダーの役割とは?
メンバーを牽引するチームリーダーの役割とは? オンライン研修とは?オンライン研修のコツ
オンライン研修とは?オンライン研修のコツ ニューノーマルとは?ポストコロナ時代の新たな働き方とその課題
ニューノーマルとは?ポストコロナ時代の新たな働き方とその課題 VUCAの時代に力を発揮できるミドルマネジメント~思考できるマネージャーとは~
VUCAの時代に力を発揮できるミドルマネジメント~思考できるマネージャーとは~ 新人エンジニアに求められる学び続ける力と論理的思考力 〜インプル社が語るAI時代に必要なスキル〜
新人エンジニアに求められる学び続ける力と論理的思考力 〜インプル社が語るAI時代に必要なスキル〜 未来塾 エバンジェリスト インタビュー:「正解より“問い”を持つ力を」未来を創るリーダーに求められる思考とは
未来塾 エバンジェリスト インタビュー:「正解より“問い”を持つ力を」未来を創るリーダーに求められる思考とは