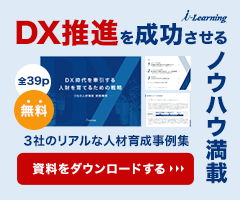デジタル人材未来塾 第一回未来交流会 レポート:未来をデザインするDNA 〜2030年のテクノロジー・社会・顧客
2025.02.25お役立ち情報
先日、弊社の会員制コミュニティ「デジタル人材未来塾」にて「未来交流会」を開催しましたので、その開催内容をレポートさせていただきます。
弊社アイ・ラーニングは研修サービスを提供する企業ですが、知識の伝達だけでなく、人と人がつながる場をつくることも大切だと考えています。そこで昨年、新たなコミュニティ「未来塾」を立ち上げています。日々の業務に追われていると、どうしても目の前のタスクや数値に意識が向きがちかと思います。けれど、それだけでは想像力が失われていってしまいます。時には顔を上げて、10メートル、20メートル先の未来を見つめる時間が必要だと考えています。
未来塾は、そんな視点を持ち新たなアイデアを生み出す場とするために構成された、講演会やディスカッション、レポート頒布、研修などを含んだ複合的なプログラムです。
講演パート:未来をデザインするDNA 〜2030年のテクノロジー・社会・顧客
講演者:コミュニティエバンジェリスト 落合和正氏 未来は私たちが決める——そんな視点から、今回の未来交流会では「バックキャスティング(未来からの逆算)」をキーワードに、2030年のテクノロジー、社会、そして消費者の変容について考えました。
未来は私たちが決める——そんな視点から、今回の未来交流会では「バックキャスティング(未来からの逆算)」をキーワードに、2030年のテクノロジー、社会、そして消費者の変容について考えました。
エバンジェリストである落合和正氏は、IBM研究所での経験や戦略コンサルタントとしてのキャリアをもとに、未来のビジョンを語りました。テクノロジーの進化がもたらす影響だけでなく、日本の経済・社会課題についても言及し、参加者と共に未来の可能性を探りました。
1.バックキャスティング:未来をヘッドライト思考で捉える 私たちはつい、過去の延長線上に未来を考えがちですが、それでは大きなイノベーションは生まれません。そこで、未来の理想の姿を描き、そこから現在の行動を逆算する「バックキャスティング」が重要になります。例えば、2030年にシンギュラリティ(技術的特異点)が訪れるとしたら、その未来を前提に今何をすべきかを考えることが求められます。この思考プロセスに基づき、未来のテクノロジー、消費者、社会の変化を見ていきました。
私たちはつい、過去の延長線上に未来を考えがちですが、それでは大きなイノベーションは生まれません。そこで、未来の理想の姿を描き、そこから現在の行動を逆算する「バックキャスティング」が重要になります。例えば、2030年にシンギュラリティ(技術的特異点)が訪れるとしたら、その未来を前提に今何をすべきかを考えることが求められます。この思考プロセスに基づき、未来のテクノロジー、消費者、社会の変化を見ていきました。
2.テクノロジーの進化とその影響
2030年に向けて、さまざまな分野で技術革新が進んでいます。特に、生成AIの進化は目覚ましく、個人のアシスタントとしての「プライベートAI」の普及が予測されています。また、量子コンピュータの社会実装により、金融・創薬・物流の最適化が加速し、従来のコンピュータでは解決できなかった問題が短時間で解決される未来が見えています。
さらに、遺伝子編集技術(Crispr-CAS9)の発展により、老化を抑制し、健康寿命を延ばす研究が進められています。2040年代には「年を取らない」選択肢が現実のものとなる可能性もあります。宇宙ビジネスも加速しており、日本でもスペースポート(宇宙港)の建設が進められています。これにより、30分でニューヨークに行ける時代が到来するかもしれません。
3.消費者の変容とライフスタイルの変化 消費者の価値観も大きく変わりつつあります。特に、ライフシフトの考え方が広まり、人生100年時代における生き方の多様性が強調されています。FIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指す人が増え、柔軟な働き方を求める傾向が強まっています。
消費者の価値観も大きく変わりつつあります。特に、ライフシフトの考え方が広まり、人生100年時代における生き方の多様性が強調されています。FIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指す人が増え、柔軟な働き方を求める傾向が強まっています。
また、ジョブ型雇用が拡大し、職務に応じた契約が一般化することで、スキルの重要性が増しています。リスキリング(学び直し)を通じて市場価値を高めることが求められる時代に突入しているのです。
4.社会の変容と日本の未来
日本では人口減少が深刻な課題となっています。毎年約70万人が減少し、2030年には「おひとりさま」の割合が全人口の4割に達するという予測もあります。認知症患者が急増し、その保有資産が200兆円を超える可能性も指摘されており、社会保障のあり方を根本的に見直す必要があります。
一方、世界の覇権争いを俯瞰すると、ヨーロッパは法と倫理の支配を強化し、アメリカは情報・プラットフォーム経済の覇権を握っています。中国は製造業の分野で優位性を持ち、中東・アフリカは資源を中心に影響力を拡大しています。こうした中で、日本がどこで競争力を発揮するのか、その答えを見つけることが求められています。
5.これからの社会に必要なこと
現代の民主主義と資本主義は、高齢層の増加により、若者の声が政治に反映されにくくなり、社会の持続的な発展が難しくなっています。この課題に対する一つの提案として、投票権に「余命」を考慮する仕組みを紹介しました。たとえば、120歳を上限とし、20歳には100票、90歳には30票を割り当てることで、未来を担う世代の意見をより反映しやすくするという考え方です。
また、ベーシック・インカムの進化系として、すべての日本人が月額10万円を「消費」ではなく「投資」に充てる仕組みも考えられます。教育、スタートアップ、次世代支援、インフラ強化など、未来への成長を促す分野に資金を振り向けることで、単なる分配ではなく、持続的な経済発展を目指すものです。
今後は、知識と経済の循環を生み出し、学びを共有しながら成長する社会を築くことが重要です。社会の変革には、現状と理想のギャップを埋める方法と、理想のビジョンを先に描き、そこへ向かう方法の二つがあります。これまでは現状を改善するアプローチが主流でしたが、今後はビジョンを描き、その実現に向けて行動する「ビジョン型」のアプローチがより重要になっていきます。
「利他的自己中」──つまり、自分の利益を追求しつつ、それが社会全体の発展にもつながる行動を取ることが、新たな時代の原動力となります。今こそ、未来を逆算し、新たな一歩を踏み出す時ではないでしょうか。
ディスカッションパート
今回のディスカッションでは、落合氏の講演を受けて、未来の企業価値、人材と組織、テクノロジー、データ経済という4つのテーマを通じて、参加者が4チームに別れて現代社会の本質的な課題について話し合いました。最後には話し合った内容をそれぞれ発表しました。
1.未来の企業価値と競争優位性 企業の価値とは何か。その本質を探るべく、このグループでは「いい企業とは何か」をテーマに議論を行いました。社員を大切にする企業、信頼を築く企業、感動を与える企業。さまざまな意見が交わされましたが、共通して浮かび上がったのは、エッセンシャルで人間が欲しがる価値を追求していったところが残っていくのではという話でした。
企業の価値とは何か。その本質を探るべく、このグループでは「いい企業とは何か」をテーマに議論を行いました。社員を大切にする企業、信頼を築く企業、感動を与える企業。さまざまな意見が交わされましたが、共通して浮かび上がったのは、エッセンシャルで人間が欲しがる価値を追求していったところが残っていくのではという話でした。
また、感動を生み、人を喜ばすような、応援される企業の在り方を追求することが、企業価値を高める鍵になると考えました。
2.未来の人材と組織変革
技術の進化が指数関数的に加速する現代において、「求められる人材」とはどのような人材なのか。この問いに対して、このグループでは「変化に適応できる人材」「新しい知識を吸収し続ける人材」という視点が挙げられました。
そして、これからの組織のあり方についても議論が交わされました。組織はよりフラット化し、個々のスキルを最大限に活かせる形へと変化していきます。その中で求められるのは、自発的にリーダーシップを発揮し、自らの役割を定義できる人材です。リスキリングの重要性も強調され、スキルを身につけることが組織の変革につながるとの認識が共有されました。
さらに、継続的に学ぶためには、「楽しい」ことが不可欠であるとの意見もありました。学びが義務ではなく、喜びとなる環境を整えることが、強い組織をつくる上での大きな課題であるといえます。
3.テクノロジーと社会課題
テクノロジーはどのように社会課題を解決するのか。このテーマのもと、このグループでは、具体的な課題とその解決策について議論しました。人手不足、介護の課題、技術格差――。現代社会が抱えるこれらの問題に対し、AIやIoT、ロボットなど、自動化技術を活用することで解決の糸口を見出せるのではないかと考えました。
また、共感の重要性についても議論がありました。企業が単に技術を提供するのではなく、人々の共感を得られるかどうかが、競争力の源泉になるという話が出ました。また、技術を活かしながら、社会とのつながりを意識したアプローチが求められる時代に突入していると考えています。
4.データ経済と未来のビジネスモデル
「データは21世紀の石油」と言われるように、データの活用はビジネスの根幹を成すようになりました。しかし、その取り扱いには慎重な姿勢が求められます。このグループでは、個人の検索データや購買データが大量に収集・活用される現状について議論しました。リコメンド機能やターゲティング広告は便利である一方で、過度な監視と感じる人も少なくありません。プライバシーの保護とデータ活用のバランスをどのように取るかが今後の課題となります。
また、データを活用する企業の責任についても話し合い、活用したいと思っている企業にとっても個人にとってもお互いにウィンウィンな正しいデータの使い方が、きちんと広まっていく世界になればいいと考えました。
まとめ
未来は偶然に訪れるものではなく、私たち自身が意識的にデザインし、創造するものです。今回の未来交流会は、2030年に向けたテクノロジー、社会、消費者の変容という壮大なテーマの下、バックキャスティング手法を活用して理想の未来像を描く貴重な機会となりました。
講演パートでは、落合和正氏が未来への洞察を示し、単なる予測に留まらず、現時点から実践すべき具体的な行動案が提案されました。技術革新の加速、不老不死、宇宙ビジネスの進展など、これからのシナリオは現代にとって大きな挑戦であり、同時に無限の可能性を秘めています。これらの革新が社会全体の構造を変え、企業や個人に新たな価値創造の原動力をもたらすと実感された方も多かったかと思います。
また、ディスカッションパートでは、多角的なテーマに基づいて参加者が活発に議論し、企業の本質的な価値提供、変化に柔軟に対応する人材の重要性、テクノロジーとデータ活用の可能性およびその倫理的課題などについて活発に議論されました。
参加者からは、
「異業種の方とざっくばらんに話すことで、新たな発想が生まれた」
「遠い未来の話だと思っていたことが、実はすぐ近くにあると気づいた」
「SFのような未来がすぐそこに来ていると感じる一方で、目の前の現実が未来を制限しているのではないかと考えさせられた」
といった声が寄せられました。
特に「学びは最高のぜいたく」という言葉が印象に残ったという意見が多くありました。日々の業務では得られない視点や発想に触れ、思考がほぐれる機会になったと感じた方も多かったようです。
最後に
 未来を考え、語り合うことは、それ自体が新たな行動のきっかけになります。また、未来は決まっているのではなく、「我々が決める」ものであり、積極的に創造する姿勢が必要かと思います。
未来を考え、語り合うことは、それ自体が新たな行動のきっかけになります。また、未来は決まっているのではなく、「我々が決める」ものであり、積極的に創造する姿勢が必要かと思います。
さらに、「利他的自己中」という視点は、各自が自らのビジョンを具体化する一歩を踏み出すことで、理想と現実のギャップを埋め、持続可能な社会の実現へ大きく前進することにつながると考えられます。
未来は、今この瞬間の選択と行動の積み重ねでつくられます。テクノロジーの進化や消費者の価値観の変化など、さまざまな要素を広く捉えながら、共に未来を築いていくことが、私たち全員の使命であり、挑戦なのではないでしょうか。
・デジタル人材未来塾
https://www.i-learning.jp/service/community-miraijuku/
アイ・ラーニング コラム編集部


 メンバーを牽引するチームリーダーの役割とは?
メンバーを牽引するチームリーダーの役割とは? オンライン研修とは?オンライン研修のコツ
オンライン研修とは?オンライン研修のコツ ニューノーマルとは?ポストコロナ時代の新たな働き方とその課題
ニューノーマルとは?ポストコロナ時代の新たな働き方とその課題 VUCAの時代に力を発揮できるミドルマネジメント~思考できるマネージャーとは~
VUCAの時代に力を発揮できるミドルマネジメント~思考できるマネージャーとは~ 新人エンジニアに求められる学び続ける力と論理的思考力 〜インプル社が語るAI時代に必要なスキル〜
新人エンジニアに求められる学び続ける力と論理的思考力 〜インプル社が語るAI時代に必要なスキル〜 未来塾 エバンジェリスト インタビュー:「正解より“問い”を持つ力を」未来を創るリーダーに求められる思考とは
未来塾 エバンジェリスト インタビュー:「正解より“問い”を持つ力を」未来を創るリーダーに求められる思考とは