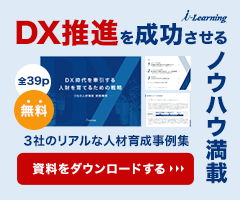【メタエンジニアの戯言】「『新しい』への懸念」は本当に新しいのか
2025.05.07松林弘治の連載コラム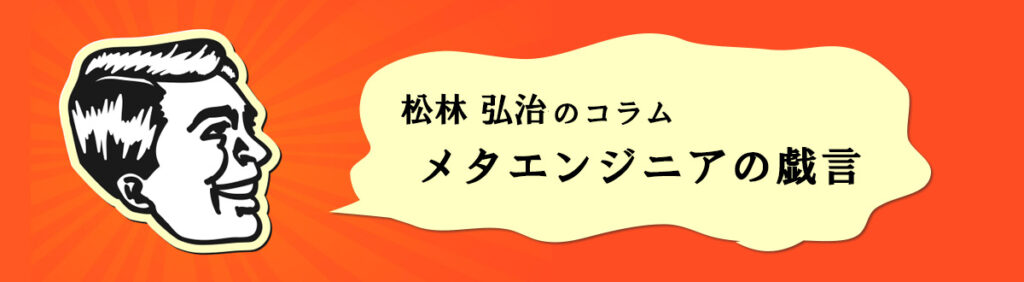
1901年、奇妙なニュースが世界を駆け巡りました。トルコ(当時はオスマン帝国)がタイプライターの輸入を禁止したというのです。
実際の新聞記事の一例は、Colorado Historic Newspaper Collectionのアーカイブで読むことができます。
その記事によると、手書きの文書は筆跡などから筆者を特定できる一方で、タイプライターで作成された文書は匿名性が高く、帝国を転覆させるような扇動的な文章が匿名で作成される恐れがあり危険だと税関当局が判断し、輸入を禁止したということでした。
どこか既視感を覚えるエピソードではないでしょうか。新しい技術の登場時には好奇心とともに、恐怖や猜疑心による拒否反応も見られる、そんな典型例と言えるかもしれません。
ーーー
似たようなエピソードとして、卓上電卓が身近になり始めた1970〜80年代のさまざまな反応もあげられます。
米国教育現場における電卓活用の歴史的変遷を詳しく調べたものに、2011年のセダービル大学の修士論文があります。それによると、一般家庭で電卓が普及しつつあった1975年頃には、「数学の基礎を教えた上で電卓を活用すれば生徒の学習意欲向上や現実的問題への挑戦につながる」と肯定する教育者がいた一方、「早期からの電卓使用は基礎計算力や暗算能力、数的感覚の育成に悪影響を与える」「生徒が電卓に依存する懸念がある」と批判する教育者も少なくなかったそうです。
その後も電卓の教育効果について研究が進められるなか、 1986年には、小学校低学年での電卓使用に抗議する数学教師たちによるデモ行進も報じられています。
1986年には、小学校低学年での電卓使用に抗議する数学教師たちによるデモ行進も報じられています。
ただし否定派は電卓使用そのものに反対していたのではなく、算数や数学の初学者はまず電卓を使わずに基礎的概念を理解するべきであり、早すぎる電卓使用が概念理解の妨げになるという懸念を抱いていたのです。
教育現場での電卓使用に関する研究や議論は一進一退を繰り返しながら発展し、2001年に発表された米国教育省の報告書では「8年生(中学2年生)で電卓を頻繁に使う生徒ほどテストの成績が良い」という結果も導かれました。しかし依然として、教師や保護者の間には「将来のために手計算ができるようにしておくべき」という意見が根強く残っています。
ーーー
繰り返しになりますが、非常に既視感のあるエピソードと感じられないでしょうか。
これはまさに、現代における生成AIへの賛否両論の反応そのもののようです。むしろ、生成AIに対する反応の方がさらに複雑で、倫理性、プライバシーやセキュリティ、バイアス、信頼性、ブラックボックス化、人間の創造力やスキルの低下、雇用や経済構造への影響、知的財産権など、多様な懸念や価値観の相違が混在しているのが特徴といえそうです。
ーーー
今後、生成AIがどのように進化発展をとげてしまうのか、われわれ人類はそれらとどのように付き合っていくことになるのか、そして社会にどのようなインパクトをもたらすことになるのか。未来予測は非常に困難です。
しかし、「可能性とリスクを併せ持ち、大きな効果と変化をもたらす技術が現れたのは、生成AIが初めてではない」ということを、100年以上前のタイプライター輸入禁止令や、50年前の米国教育界における電卓使用をめぐる議論を通じて再確認した次第です。

松林 弘治 / リズマニング代表
大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期過程修了、博士後期課程中退。龍谷大学理工学部助手、レッドハット、ヴァインカーブを経て2014年12月より現職。コンサルティング、カスタムシステムの開発・構築、オープンソースに関する研究開発、書籍・原稿の執筆などを行う。Vine Linuxの開発団体Project Vine 副代表(2001年〜)。写真アプリ「インスタグラム」の日本語化に貢献。鮮文大学グローバルソフトウェア学科客員教授、株式会社アーテックの社外技術顧問を歴任。デジタルハリウッド大学院講義のゲスト講師も務める。著書に「子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい」(KADOKAWA)、「プログラミングは最強のビジネススキルである」(KADOKAWA)、「シン・デジタル教育」(かんき出版)など多数。


 【メタエンジニアの戯言】「感想を噛み締め、批判から学ぶ」
【メタエンジニアの戯言】「感想を噛み締め、批判から学ぶ」 【メタエンジニアの戯言】「個別指導」最強説
【メタエンジニアの戯言】「個別指導」最強説 【メタエンジニアの戯言】生成AIと外注の共通点
【メタエンジニアの戯言】生成AIと外注の共通点 【メタエンジニアの戯言】ますます「考えない」世界へ
【メタエンジニアの戯言】ますます「考えない」世界へ 【メタエンジニアの戯言】確率論的に動く生成AIで決定論的プログラムを作る不思議
【メタエンジニアの戯言】確率論的に動く生成AIで決定論的プログラムを作る不思議 【メタエンジニアの戯言】DM文化と公開チャンネル文化は対立項か
【メタエンジニアの戯言】DM文化と公開チャンネル文化は対立項か