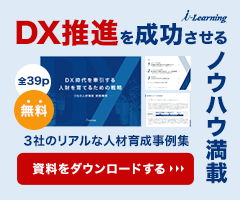講師インタビュー:価値共創を実現するIT部門 ― ITIL® 4の基礎で変わるサービス提供の視点 ―
2025.09.22IT , お役立ち情報
株式会社アイ・ラーニング
ITサービスマネジメント講師 小倉 紀彦 インタビュー

「ITILはもう古い」「実際の現場では活かしにくい」——そう感じている方も多いかもしれません。
しかし、ITIL®4では「価値共創」や「柔軟なサービス運用」がフレームワークの核に据えられ、DX時代にこそ活かせる思想へと進化しています。
IPA『デジタルインフラ白書2024』では、サービスマネジメントに関するスキル不足を課題とする企業が6割を超えているとされており、IT部門の役割は“提供者”から“共創のパートナー”へ変化しています。
今回は、ITサービスマネジメント研修を担当する講師・小倉に、「ITIL® 4が示すサービス提供の新しい視点と人材育成のポイント」について話を聞きました。
――まず、「価値共創を実現するIT部門」とは、どのような姿でしょうか?
小倉:依頼された機能要件を提供するのではなく、ビジネス部門や顧客と一緒に「何が本当に必要か」を考え、サービスとして形にしていく姿ですね。 ITIL® 4は“サービス消費者との共創”を強調しており、IT運用にとどまらずビジネスと一体化して価値を生み出すことに焦点を当てています。
――ITIL 4では、どのようにその考え方が設計されていますか?
小倉:大きな特徴は、「サービスバリューシステム(SVS)」という全体設計のフレームワークです。従来の“プロセスの積み重ね”ではなく、価値を起点に考える枠組みです。たとえば、「ガイディング・プリンシプル」と呼ばれる7つの原則では、「価値に着目する」「フィードバックを得ながら進化する」「現状から始めていく」など、変化の激しい環境でどう動くかの指針が示されています。
――このような設計思想は、実際の現場にどのように活きるのでしょう?
小倉:たとえばプロジェクトで「なぜこれをやるのか」「誰にどんな価値を届けるのか」があいまいなまま進むこと、ありますよね。ITIL® 4の考え方を取り入れると、企画や開発、運用といった立場の違うメンバーが共通のビジョンを持ちやすくなります。それが結果的に、サービス品質やスピードの向上につながるんです。
――DX時代にITサービスマネジメントを学ぶ意義はどこにあると思いますか?
小倉:今のIT部門には「運用管理」だけでなく「変革への対応力」が求められています。クラウド、アジャイル、DevOpsなど、取り巻く技術も急速に変わりつつあります。IT部門はむしろ変化の旗振り役になる必要があり、その土台として、ITサービスマネジメントの知識や視点が欠かせないんです。
――人材育成の観点で重要なポイントは何でしょう?
小倉:“ルールを守ること”ではなく、“状況に応じて判断できる力”を育てることです。ITIL® 4のガイディング・プリンシプルはその土台になりますし、研修でも「型にハメる」のではなく「現場で活かせる問いの立て方」を重視しています。
先ほども述べましたが「現状からはじめる」などの原則を理解するとUSJの後ろ向きで走るジェットコースターの理由もわかってくるので、ITILを身近に感じられるとともに業務に活かしていく意義もわかると思います。
―― ITIL®研修の知識が現場で活かされにくいのはなぜですか?
小倉:よくあるのは、試験合格で終わってしまう“学び切り”の状態になりがちだからです。
大事なのは「知識を現場に結びつける仕組み」を整えることです。
本来の目的は、ITサービスを安定的に、価値あるものとして提供し続けられる組織をつくること。その視点が欠けると、学びも自己完結してしまいます。
――では、研修の成果を現場につなげるポイントは?
小倉:ポイントは“構造設計”です。個人の理解やスキルに依存せず、現場で再現性のある形にしていく必要があります。
たとえば、
- アクションプランをチーム単位で設計する
- I部門共通の行動指針をつくる
- 成果指標(KPI/KGI)と日々の業務改善をつなげる
といった設計が有効です。
――日本企業がITIL®を導入する際につまずきやすい点は?
小倉:「正しくやること」にこだわりすぎる点です。ITIL®は“ベストプラクティス”であり、全部を完璧にやる必要はありません。
必要な部分から小さく試し、成果を積み重ねて次につなげるように仕組化することが大切です。例えば大きな成功や成果を求めすぎてギャンブル的な活動をするのではなく、「小さくてもいいので確実」に成功·成果を求めて行動することも大切です。そしてこの成功を次の活動に活かすことです。
――人材育成で今企業が持つべき視点は何ですか?
小倉:「役割を超えた理解」と「継続的改善の文化づくり」ですね。サービスを作る人、使う人、支える人が同じ価値観で動けるようにする。そのために、共通言語としてのITIL®や、仕組みづくりの技術が必要なんです。
―研修後に、現場が“自走”できるようにするには?
小倉:大事なのは、「考える軸」と「小さく試す勇気」を現場に渡すことです。
IPAの『企業IT動向調査報告書2024』では、IT人材育成の最大の障壁は「職場での実践機会の不足」とされています。
新しい取り組みは、まず優先順位を決めて、小さく始める。そして、小さな成功を積み重ねて次につなげる。このサイクルを何度も回すことが重要です。成功体験を積み重ねていくことが自走力につながります。
――最後に、人事・教育担当者へのメッセージをお願いします。
小倉:「ITIL®を完璧に教えよう」と思う必要はありません。大切なのは「現場でどんな価値を実現したいか」を一緒に考えることです。ITILは価値共創を実現するための“育てる土台”であり、現場に合わせて自分たちの言葉で活用してほしいと思います。
アイ・ラーニングのITサービスマネジメント研修
アイ・ラーニングでは、ITサービスマネジメントに関する研修を多数ご用意しています。
ITIL® 4をはじめとしたフレームワークに基づきながら、現場で使える視点や組織で活かせる仕組みづくりをテーマに、課題に応じた研修をラインナップしています。
たとえば、IT部門のリーダー育成、サービス品質向上、他部門との連携改善といった課題に対して、実践的な演習とケーススタディを交えたコースをご提供しています。自社の課題を「価値共創」の視点でとらえ直したい方は、ぜひ一度詳細をご覧ください。


 Society 5.0/第四次産業革命とは?実現のために必要なこと
Society 5.0/第四次産業革命とは?実現のために必要なこと DX人材とは?人材不足の背景と育成方法、必要なスキルについて解説
DX人材とは?人材不足の背景と育成方法、必要なスキルについて解説 マネジメントの聴く力・伝える力を変えるフィードバックとは
マネジメントの聴く力・伝える力を変えるフィードバックとは 自社のITリテラシーに不安を持つDX人材育成担当者に捧げる~失敗しないDX人材育成 虎の巻~
自社のITリテラシーに不安を持つDX人材育成担当者に捧げる~失敗しないDX人材育成 虎の巻~ 「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~実践企業の事例から紐解くカスタマーサクセスの最前線
「カスタマーサクセス」を実現させる人材育成方法とは? ~実践企業の事例から紐解くカスタマーサクセスの最前線 未来にワクワクする働き方とは? 〜 変化の時代の人づくり、「活学」は学ぶ心のスイッチ〜
未来にワクワクする働き方とは? 〜 変化の時代の人づくり、「活学」は学ぶ心のスイッチ〜