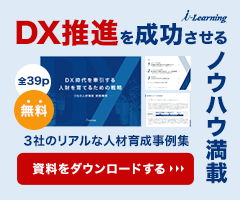SaaSとは?似たサービスとの違いやメリット・デメリットを解説
2025.05.15IT
多くの企業で導入が進んでいる「SaaS(サース/サーズ)」。業務効率の向上やアクセスのしやすさなどさまざまなメリットがありますが、SaaSは多岐にわたっているためわかりにくいと感じている人もいるかもしれません。本記事では、SaaSの基本的な仕組みや特徴、PaaSやIaaSなど他のクラウドサービスとの違い、メリット・デメリットについて解説します。
SaaSとは? SaaSの主な特徴
SaaS(Software as a Service)とは、サービス提供者のサーバーで稼働しているソフトウェアを、インターネットなどのネットワークを経由して利用する形式のサービスです。ソフトウェアをインストールする必要がなく、ネットワークを経由してアクセスすればサービスを利用できます。SaaSには、主に次のような特徴があります。
インターネット環境があればどこからでもアクセス可能
SaaSは、WebブラウザなどからIDとパスワードでアクセスする仕組みです。そのため、インターネット環境のある場所であればどこでも利用することが可能です。在宅ワークをする場所や出張先、客先など会社外からもアクセスできることから、利便性や業務効率の向上を図れます。
複数人で同時に作業可能
SaaSでは複数の利用者が同時にアクセスし、リアルタイムでファイルの閲覧や編集、データ共有が可能です。Web会議システムを用いれば、複数人でリモート会議や共同作業をスムーズに行えます。
SaaSと似たサービスとの違い

SaaSに似たサービスに、IaaSやPaaSがあります。MaaSなど他の「〇aaS」もありますが、SaaSと関連するのはIaaSとPaaSの2つです。
IaaSとの違い
IaaS(Infrastructure as a Service)は、情報システムの構築に利用できる仮想サーバーやストレージ、ネットワークといったインフラを提供するサービスです。SaaSは、IaaSのインフラに加えて、プラットフォームやソフトウェアを含めたサービスと考えるとわかりやすいでしょう。
PaaSとの違い
PaaS(Platform as a Service)は、ソフトウェアを実行するためのプラットフォームを提供するサービスです。PaaSはサーバーやデータベース、ミドルウェアなどIaaSのサービスに加え、開発環境や運用のための環境をサービスとして提供しています。SaaSは、PaaSの機能を有しつつソフトウェアも提供しているサービスです。
SaaSのメリット
オンプレミスで情報システムを構築する場合に対し、SaaSを利用した場合のメリットをご紹介します。
導入コストが安価
オンプレミスでシステムを構築する場合には、高価なサーバーやネットワーク環境が必要となり、コストがかかります。一方SaaSの多くは料金体系を月額や年額といったサブスクリプション制にしており、必要な期間だけ利用できるという仕組みになっています。またサーバーやソフトウェアなどの購入が不要であることから、オンプレミスでシステムを構築する場合と比較して導入コストを安くできるでしょう。
保守運用の負担が少ない
SaaSにかかわるサーバーやネットワークなどのメンテナンス、セキュリティ対策は、サービス提供者側が実施します。オンプレミスのように保守・運用する必要がないため、利用者側の負荷を減らせます。
常に最新版を利用可能
SaaSは提供者側でアップデートやバージョンアップを行い、利用者は常に最新版を利用できます。アップデートの内容はバグの修正をはじめ、新機能の追加やUIの改善などです。オンプレミスでシステムのアップデートを行う場合には、関係するサーバーやデバイスも漏れなくアップデートをかける手間がかかりますが、SaaSではその手間も省かれます。
SaaSのデメリット
SaaSを導入する場合には以下のデメリットも認識しておく必要があります。
セキュリティ対策が必要
SaaSはサービス提供者側がインフラなどに対してセキュリティ対策を施していますが、利用者側でもセキュリティ対策を行う必要があります。
たとえばアクセス管理についてです。IDやパスワードの管理が適切でない、あるいは利用者に対してアクセス権が適切に設定できていない場合には、情報を不正に持ち出されるリスクがあります。またバックアップについても、SaaSサービスの停止や重要なデータが消失するケースが考えられるため、社内でもバックアップを保存しておくことが必要です。あるいは、SaaSサービス側で提供されていれば、バックアップに関するオプションサービスを利用することも選択肢として考えられます。
SaaSサービスを導入する際にも、サービス提供者の信頼性を確認しておくことが必要です。事業者の信頼性の確認には、ISMSクラウドセキュリティ認証(ISO / IEC27001)やCSマーク(クラウドセキュリティ・マーク)、CSA STAR認証(CSA Security)といった認証制度を確認しておくとよいでしょう。またSaaSサービスの導入実績もチェックしておきたいところです。
サービス乗り換えが難しい場合がある
SaaSサービスから別のサービスへ乗り換える際、さまざまな原因で移行が難しい場合があります。たとえば利用者が快適に現状のサービスを利用していて慣れていると、別のサービスを受け入れがたくなりがちです。またSaaSサービスがそのサービスと互換性がない場合には、一から情報システムを再構築しなければなりません。ほかにSaaSに蓄積されたデータが膨大であることなどから、そもそも移行が難しいというケースもあります。
サービスを乗り換えるケースは自社都合だけでなく、サービスやサポートの終了、破産といったSaaSサービス提供者側の事情もあります。突然サービスを乗り換えなければならなくなった場合には、サービスの乗り換えやデータ移行をサポートしてくれる事業者を選ぶことが重要です。
SaaSの代表的なジャンル

SaaSの代表的なジャンルと、サービスをいくつかご紹介します。
業務支援系SaaS
会計や顧客管理、営業活動などを効率化したり、より深い分析を実現したりするSaaSです。代表例はCRM「Salesforce」などがあげられます。
マーケティング系SaaS
マーケティング系SaaSとしては、マーケティングオートメーションサービス(MA)や、Webマーケティングにおけるアクセス解析などが挙げられます。主要サービスは、米国発の大手サービス「HubSpot」などがあります。
EC・販売管理系SaaS
2023年の日本国内の市場規模は前年比9.23%増の24.8兆円と、大きく伸びる市場であるEC領域でも、SaaSが使われています。この領域のSaaSといえば、「Shopify」があります。ECサイトの運営から出店における機能が網羅的に搭載されています。
人事労務系SaaS
その名の通り、勤怠管理や人材管理などの人事労務業務を支援するものです。勤怠をはじめとする人事労務に特化した「SmartHR」などがあります。
コミュニケーション系SaaS
社内や社外のコミュニケーションに活用するSaaSです。コミュニケーション系SaaSは、チャットツールとオンライン会議システムに大別されます。前者は「Slack」などが主流のツールです。
コラボレーション系SaaS
プロジェクトやタスクの管理、ファイル共有およびドキュメントの整理などに使うのが、コラボレーション系ツールです。代表例は、無料プランもありまず始めやすい外資系ツール「Notion」です。
まとめ
SaaSについて簡単にご紹介しました。SaaSの活用は、DX推進や業務効率化にも有効です。自社の目的や課題に合ったサービスを見極め、導入を検討してみてはいかがでしょうか。なおSaaSを効果的に活用するためには、利用者側にも一定の知識やスキルが求められます。スムーズな導入と運用のために、社内研修の準備も視野に入れておくと安心です。
クラウド/クラウドネイティブ研修についてはこちらから
👉https://www.i-learning.jp/courses/it/cloud/
ITスキル研修についてはこちらから
👉https://www.i-learning.jp/courses/it/
アイ・ラーニングコラム編集部