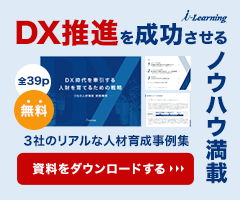離職防止とは?効果的に行う方法や従業員が離職する原因を解説
2025.09.09ビジネス
管理職や人事担当者にとって、従業員の離職は単なる人事上の問題ではなく、企業経営における重要な課題の一つとなっています。しかし、離職を決断する理由は従業員によって異なるため、画一的な対応ではなく、個人への理解と柔軟な対策が必要です。
本記事では、離職防止の基本的な考え方から従業員が離職する主な原因、そして効果的な離職防止策までを体系的に解説します。
離職防止とは
離職防止とは、企業が従業員の自発的な退職を防ぐために実施する施策や対策のことを指します。単に従業員の退職を阻止するだけでなく、従業員が長期的に働き続けたいと思える職場環境を整備し、組織への愛着と貢献意欲を高めることを目的としています。また、企業の競争優位性を維持し、組織の持続的な成長を実現させるためにも欠かせない取り組みです。特に人材不足が深刻な業界や、優秀な人材を長期的に確保したい企業にとって、非常に重要な経営課題の一つといえます。従業員一人ひとりのニーズに合わせた対策を講じることで、より効果的な離職防止につながるでしょう。
離職防止が必要である理由
離職防止が企業経営において重要視される理由は、従業員の離職が企業に与える多面的な影響にあります。以下に主な理由を詳しく解説します。
優秀な人材の流出
従業員の離職は、企業の技術力低下、生産性の低下、顧客との関係喪失、イノベーション創出能力の減少につながります。特に、経験豊富な人材が持つ専門知識やノウハウは企業にとって貴重な無形資産であり、企業の競争力低下に直接影響を及ぼす可能性が高いです。また、優秀な人材が競合他社に転職した場合、営業秘密や事業戦略、取引先が他社へ流れてしまうリスクも存在します。
既存社員の負担増加
従業員が離職すると、離職した人が担当していた業務を他の従業員が引き継ぐことになります。人員補充が行われるまでは、一時的に既存社員の負担増加が懸念されます。過度な負担は、既存社員のストレスの蓄積、集中力やモチベーションの低下を招きます。結果として、離職の連鎖を引き起こすリスクがあります。
企業のイメージ低下
離職率が高い企業は、「働きにくい職場」「長く働き続けることが難しい職場」というマイナスのイメージを持たれがちです。転職活動の際、求職者は離職率を判断材料の一つとして考えるため、採用活動が難航するおそれがあります。また、従業員の入れ替わりが激しい企業は、顧客や取引先からの信用低下にも影響を与える可能性があります。
離職にかかるコストが発生する
従業員の離職にはさまざまなコストが発生し、企業にとって経済的負担となります。新たに人材を確保するための採用コストだけでなく、研修・教育にかかる育成コスト、外注コストなども挙げられます。これらのコストを抑えるためにも、長期的な定着に向けた施策に力を入れることが必要です。
従業員が離職する原因

従業員が離職を決断する原因はさまざまで、個人の状況や価値観によって異なります。主に離職の原因とされる要素を理解することで、効果的な離職防止策を講じることが可能になります。
労働条件
労働条件に関する不満は、離職へつながる主な原因の一つです。例えば、長時間労働や残業過多、給与・福利厚生への不満、有給休暇の取得困難、リモートワークの可否、ワークライフバランスが取れないなどが挙げられます。同業他社や市場相場と比較して労働条件が適切に整備されていない企業は、従業員のモチベーションや意欲を削ぎ、優秀な人材の流出リスクが高まります。
人間関係
職場での人間関係は、従業員の満足度や離職率に大きな影響を与えます。上司や同僚との過度な距離感、チーム内でのコミュニケーション不足、管理職のマネジメント不足なども、人間関係を悪化させる原因です。労働条件や仕事内容が合っていても、人間関係にストレスを抱えている場合は仕事がしにくく、離職につながる可能性が高くなります。
仕事内容
仕事内容に不満を抱えている場合、従業員満足度の低下につながる原因となりやすいです。「やりたい仕事内容と実際の業務が異なる」「単調な仕事ばかり任される」という場合、従業員のやりがいや意欲が失われてしまいます。また、「昇進・昇格の道筋が不明確」「成長機会が限られている」という場合も、将来への不安が生じやすく、離職を促進させる可能性があります。
離職の可能性が高い社員の特徴
離職の可能性が高い社員には、行動や態度において共通する特徴がみられます。これらの兆候を早期に発見し、適切な対応を行うことで、離職を未然に防ぐことが可能です。
モチベーションが低下している
モチベーションの低下は、離職を考えている従業員に最も現れる特徴の一つです。具体的な変化としては、突然業務のミスが増えた、納期を守れなくなる、新しい業務を避ける、積極的な発言が減少するなどが挙げられます。以前よりも、生産性やパフォーマンスにおいて明確な低下がみられる場合は注意が必要です。
社内でのコミュニケーションが減っている
コミュニケーションの減少は、従業員の組織に対する関心の低下を示す重要な兆候です。具体的な変化としては、挨拶をしなくなる、目標に対する関心を示さなくなる、会議での発言が減少する、必要最小限の会話しかしないなどといった行動が挙げられます。このように組織の一員としての意識の希薄化がみられる場合は、離職を考えている可能性があります。
以前より業務を早めに切り上げている
以前と比較して早めに仕事を切り上げるようになった、定時で帰宅するようになったという場合も離職の可能性が考えられます。単に帰宅時間が早まっただけでなく、「業務が残っていても定時で帰宅する」「緊急性の高い業務でも残業しない」など、業務に対する責任感の低下がうかがえる場合は、特に注意が必要です。
転職活動の兆候
急な休暇取得の増加はよく見られる転職活動の兆候の一つであり、平日に一日もしくは半日休暇の取得が増えると、面接のための時間確保と考えられます。また、パソコンの使用履歴に転職サイトや求人情報サイトへのアクセスが確認される場合は、転職活動中の可能性が高いです。従業員の離職リスクを早期に察知するためにも、これらの兆候に注目し、適切なコミュニケーションや環境改善を図ることが重要となります。
離職防止を効果的に行う方法

離職防止を効果的に行うためには、従業員の離職の原因に応じた多角的なアプローチが必要です。
働き方を改善する
離職防止における重要な取り組みの一つが、働き方の改善です。長時間労働の削減、業務プロセスの見直し、有給休暇の取得促進、リモートワークやフレックスタイム制度の導入など、多様な働き方への対応が効果的です。従業員の負担を軽減し、多様な働き方の選択肢を提供することで、従業員の満足度向上と離職率の低下につながります。
また、社員が転職を選ぶ理由は外部への憧れだけでなく、社内でのキャリア形成の道筋が見えないことも大きな要因です。「この会社で成長できる」「ここで働く意味がある」と感じられるよう、社内でのスキルアップやキャリア開発の機会を積極的に提供しましょう。
コミュニケーションを活性化させる
職場内での信頼関係の構築と維持は、離職防止において極めて重要な要素です。上司や同僚との交流があることで心理的安全性が高まり、従業員の組織への帰属意識を向上させます。また、業務上の課題や悩みを早期に把握できると、個人に合った適切な支援が可能となります。定期的な1on1ミーティングの実施、メンター制度の導入、部署間の交流イベントなどを活用し、コミュニケーションを活性化させて良好な人間関係を構築しましょう。
適切な評価制度を導入する
業務に対する適切な評価は、従業員のモチベーション向上と離職防止に大きな効果をもたらします。上司の主観のみによる評価は従業員の不満につながるため、公正で透明性の高い評価制度の導入が必要です。また、評価内容のフィードバック、昇進・昇格の基準の明確化、キャリア開発機会の提供などにより、従業員満足度の向上と長期的な定着を図ることが求められます。
まとめ
離職防止の取り組みは、優秀な人材の流出防止、既存社員の負担軽減、企業イメージの向上、コスト削減などの観点からも重要な経営課題です。管理職や人事担当の方においては、自社の状況に応じて、従業員が働き続けたいと思える職場環境を整備することが重要です。
アイ・ラーニングでは、従業員の離職防止策を講じたいと考えている方に向けて、ビジネス上必須となる知識やスキルを習得できる役立つさまざまな研修を用意しています。従業員の満足度向上と長期的な定着を実現したいという場合は、ぜひお気軽にご連絡ください。
i-Learningのビジネススキル研修についてはこちら
👉https://www.i-learning.jp/courses/human/
経営財務 / 組織マネジメント 研修についてはこちら
👉https://www.i-learning.jp/courses/human/management/
アイ・ラーニングコラム編集部


 「デザイン思考」でビジネスやライフスタイルから新たな発見や未来を見出す
「デザイン思考」でビジネスやライフスタイルから新たな発見や未来を見出す セルフマネジメントの重要性と実践方法
セルフマネジメントの重要性と実践方法 ヒューマンエラー対策のポイントとは?原因や具体例から学ぶ予防策
ヒューマンエラー対策のポイントとは?原因や具体例から学ぶ予防策 人材開発支援助成金とは?制度内容や申請方法をわかりやすく解説
人材開発支援助成金とは?制度内容や申請方法をわかりやすく解説 レジリエンスとは?ビジネスにおける意味やメリット、高める方法をご紹介
レジリエンスとは?ビジネスにおける意味やメリット、高める方法をご紹介 ウェルビーイングとは?ウェルビーイングの意味や実現するための取り組み
ウェルビーイングとは?ウェルビーイングの意味や実現するための取り組み