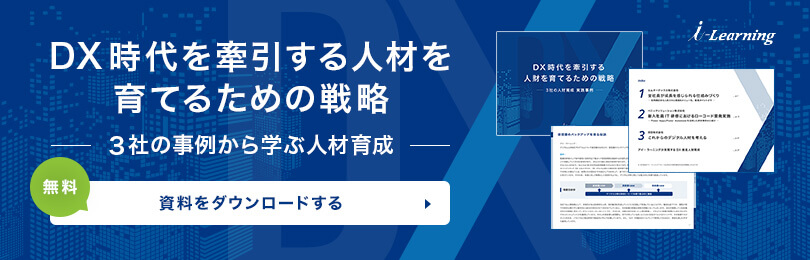日販テクシード株式会社様
川上 栞 (左)
コーポレート本部 人材戦略&マネジメント スペシャリスト
人事担当として5年にわたり、日販テクシード全社の人材育成に携わる。新卒入社時の導入教育からその後のキャリア形成まで、多様な個性と事業拡大に対応しうる育成体制を構築し、持続可能な事業成長の基盤を支える。
菅谷 沙紀 (右)
AI&C本部 人材開発 人材開発第1チーム・マネージャー
技術部門の新人担当マネージャー。IBM i技術者としての豊富な経験を持ち、2024年から会社の将来を担う新人技術者の育成を担当。新入社員研修の企画から運営までの各プロセスに技術部門の視点で関与し、新入社員の成長をサポートする役割を担う。
――まず、日販テクシードについてお聞かせください。
川上氏:当社は情報通信業に属する、システム開発や運用などのサービスを提供するシステムインテグレーション企業です。設立当初は、日販グループのIT事業を担う会社として出版関連の事業からスタートしましたが、ここ10年ほどはグループや出版業界以外にも領域を拡げており、先端技術を活用したイベントソリューションなどの事業も展開しています。
――今回取材にご協力いただいているお二方の研修における役割を教えてください。
川上氏:私は現在の部門に異動してから5年ほど、バックオフィス部門の人事として全社の人材育成を担当し、新入社員研修には企画から携わっています。主に技術部門と連携して、アイ・ラーニングとの折衝や調整をするのが役割です。
菅谷氏:私は2024年度から、技術部門の新人担当マネージャーとして研修に関わっています。1on1などで研修中の新入社員の声を吸い上げて、研修会社との窓口である川上と共に、新入社員をフォローします。企画段階では、技術部門の視点で当社の技術者として必要なスキルなどの情報を提供する役割を担いますが、自分が受けた研修からは大きく内容が刷新されているため、学びながら取り組んでいます。
アイ・ラーニングの研修を選んだ経緯と背景
――アイ・ラーニングとのお付き合いはどのように始まったのでしょうか。アイ・ラーニングを選んだ決め手などがあれば教えてください。

川上氏:2018年から、アイ・ラーニングのJavaエンジニア育成研修を利用しています。以前は新入社員研修の企画から運営まで、ほぼ内製で実施していました。しかし、IT企業の人材として必要な基礎知識(ビジネススキル・テクニカルスキル)が習得できていない、細部まで目が行き届かないなどの課題があったため、2016年から外部の研修会社を利用するようになりました。最初の2年間は別の会社にお願いしていたのですが、受講した新入社員が求めるスキルレベルに達していなかったことやコストバランスを見直し、アイ・ラーニングに切り替えました。
アイ・ラーニングを選定した理由として、まず研修内容の網羅性の高さが挙げられます。研修会社見直しの際、アルゴリズムやデータベース、テスト技法といった基礎知識の習得が課題でしたが、アイ・ラーニングの研修は「ITとは」というエンジニアリングの基礎から始まり、最後の開発演習で実務に近い経験ができる点を評価しました。当社では講義だけでなく、自分の手を動かして学ぶことを重視しているため、アクティブラーニングが取り入れられている点も評価したポイントです。
ちなみに、私自身のアイ・ラーニングとのお付き合いは、人材育成の担当になった2020年からで、当時はコロナ禍の真っ只中でした。振り返ってみれば、急遽オンラインへの切り替えを余儀なくされた時期で、研修を予定通りに実施することが大変だったと思います。そうした中でも週1回の報告会を実施し、受講者の様子や研修の進捗状況を逐一報告してくださいました。カリキュラムはもちろん、そういったフォローアップ体制が非常に丁寧だと感じています。
研修の実施効果
――社内では、新入社員研修の効果についてはどのように評価されていますか?「ここが良い」と感じている点などがあれば教えてください。
川上氏:OJT担当からは順調と聞いており、研修内容が不足しているといった指摘は今のところありません。配属後、業務知識の習得や仕事の進め方につまずくことがあっても、自分で壁を乗り越える経験も成長に必要なことだと考えていますので、基本的にはフォローしながら見守ります。だいたい2、3ヶ月で成長スピードが上がり、できることや任される役割が増えていくようです。その下地を、現在の研修で作ることができていると考えています。
人事としては、合同研修のクラスマネージャーの存在がとても良いと思っています。技術系の講師との2名体制で、テクニカルスキルとビジネススキルの両面を鍛えてもらえるのはありがたいですね。社内研修や実務に入った時には基本的なビジネススキルが身についているので、OJT担当の負担を軽減できています。
クラスマネージャーは、日報の書き方や報連相といった社会人の基礎となるビジネススキルを指導する傍ら、学級担任のような役割も担い、研修の進捗状況や一人ひとりの様子などをきめ細く報告してくださいます。

菅谷氏:研修の最後に「システム開発プロジェクト演習」としてチームで1つのシステムを作る課題があります。そこで開発の流れや報連相、役割分担などについてチームでの動き方を体験します。社内研修の開発実習では個人で1つのシステムを作りますので、アイ・ラーニング研修の中で担当しなかった役割も自分でやらないといけなくなります。つまり、合同研修でプロジェクトによる開発を体験した後、社内研修であらためて開発の全工程を把握する機会になります。開発実習としては補完できていますし、相乗効果も生まれていると感じています。
研修の感想
――研修を受講された新入社員の皆さんはどのように感じているのでしょうか?
川上氏:新入社員の中にはIT未経験で入社する人も多いです。研修のスピードについていくのが大変で「学んだことをもう少し時間をかけてアウトプットしたかった」という声もありますが、「ITの知識について一から学ぶことができ、最後の開発演習は難しかったが良い経験になった」という意見が多いです。全て個人のレベル差に合わせた研修というのも難しいため、研修内容と自己学習での底上げのバランスは永遠の課題かもしれません。
ここ数年の研修終了後のアンケートでは、新入社員全員が「満足」と回答しています。特に、合同研修で他社の新入社員と一緒に学べることが良い刺激になっているようです。チームを入れ替えながら行うアクティブラーニングを通して、さまざまな人と接することが、ビジネススキル面でもITスキル面でも役立っていると聞いています。
菅谷氏:新入社員から聞いた話ですが、合同研修で一緒に学んだ他社メンバーと、研修後も「今はこんな仕事をしている」といった近況報告などのコミュニケーションが続いているようです。これはとても良いことだと思います。
川上氏:講師のサポートが手厚いという声もよく聞かれますね。「講師の○○さんのファンになった」という人もいます。アイ・ラーニングの研修を受けた新入社員が、数年後に新人研修の担当となって、当時の講師と再会する場面もありました。成長した姿を見てもらえるのはとても良いことですので、これも長くお世話になっているメリットかなと思っています。
新入社員研修の新たな取り組み
――あらためて、新入社員の育成方針や研修内容について、具体的にお伺いしてよろしいでしょうか。
川上氏:2、3ヶ月のプログラミング中心の技術研修を経て実務につく会社も多いかと思いますが、当社では入社後の1年間を育成期間と定め、エンジニアとしての土台を築いていく育成ビジョンを持っています。約2ヶ月にわたるアイ・ラーニングの合同研修を受けた後、3~4ヶ月ほど社内集合研修を実施し、仮配属という形で、OJTに入る流れになっています。
菅谷氏:具体的には、最初にアイ・ラーニングの合同研修でITの基礎やビジネスマナーの基礎を学びます。その後の社内研修で弊社独自の開発ルールなどを説明したうえで、開発実習に入ります。実習では、一人ひとりが簡易版“X(旧 Twitter)”のようなSNSシステムを開発する課題に取り組みます。要件定義や設計から開発、最終的にAWS環境へデプロイを行うところまで、独力で行います。スキルの習得や開発プロセスを疑似体験するのと同時に、1つのものを作りあげる達成感を得てもらうことも目的の1つです。
その他にも、当社のファミリーデーに向け、生成AIを活用し子供向けのオリジナルの絵本が作成できるWEBアプリケーションを新入社員全員で作り上げました。
当日は使用した子供たちの笑顔を多く見ることができ、作成したアプリを使ってもらうという経験を通じて、自分自身の成長を感じると共に顧客視点を学ぶ機会にもなっています。
――今年は大幅に採用人数を増やし、新入社員研修のあり方にも変化があったと伺っています。具体的にはどのような形になったのでしょうか。
川上氏:例年、6~10名程度を採用してきましたが、2025年度は16名が入社しました。さらに、今後の事業拡大を見据えた人材の確保を目指して、来年以降も20名前後の採用を目標にしています。新卒採用を増やし、自社にマッチした人材を育成する方針です。
採用人数の増加により、従来通りの研修カリキュラムや体制では対応しきれない点があったため、これまで内製で行っていた研修の一部をアイ・ラーニングにお願いすることになりました。具体的には、システム開発の実習部分をカリキュラム化する支援と、研修の運営をアイ・ラーニングの講師に主導してもらい、私たちはサポート役として関わる形にしました。
菅谷氏:内容的には当社のニーズに沿ったオーダーメイドに近いもので、これまでと同じく新入社員が独力で1つのシステムを作りあげることを主眼としています。実装する機能や実習期間などの要望を当社からアイ・ラーニングに伝えて、カリキュラムを組み立ててもらいました。
川上氏:外部の力を借りて開発実習を実施するのは初めての取り組みですが、その中でもアイ・ラーニングに相談したのは、これまでの実績で培った信頼関係があったからです。他社との比較検討もしたうえで、やはりアイ・ラーニングが最適だという結論に至りました。

今後の展望とアイ・ラーニングへの期待
――今後の人材育成への展望について教えてください。その中で、アイ・ラーニングにはどのような支援を期待しますか。
川上氏:当社では、新入社員研修は体系化できており、社会情勢やトレンドのIT技術なども取り入れながら社内研修の内容も年々アップデートしています。今後は、さまざまな領域のプロフェッショナルを育成していきたいと考えており、プロフェッショナル育成に繋がるような研修をアイ・ラーニングと連携して研修を作りあげるパートナーとしての期待を持っています。
このほかには、新入社員研修の最初の2ヶ月間、アイ・ラーニングの合同研修で共に学んだ研修生同士が再会する機会があったら良いなと思っています。半年後、1年後、3年後などに、かつて一緒に研修を受けたメンバーと交流する機会があれば、良い刺激となって相乗効果が生まれると思います。そういった長期的な取り組みがあっても良いかと考えています。
多様性を尊重し、社会人としての人間力を身につける育成へ
――最後に、同じように新入社員研修を検討されている企業に向けて、メッセージをお願いします。
菅谷氏:新入社員を育成する人材が足りない、業務との兼ね合いで研修に携わる人手を確保するのが難しいといった問題を抱える会社は多いと思いますが、外部のリソースに頼る方法で解決できる場合もあります。アイ・ラーニングのような研修会社を活用することには、さまざまなメリットがあると思います。
川上氏:当社が重視しているのは、技術スキルだけでなく、ビジネススキルや個性を活かして伸ばすという点です。今は多様性の時代で、一人ひとりの価値観が異なります。そういった個性を尊重しながら育成したい、社会人としての人間力を身につけてほしいと考えている企業には、アイ・ラーニングがぴったりだと思います。
アイ・ラーニングコラム編集部
育成に関するお悩みや課題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。