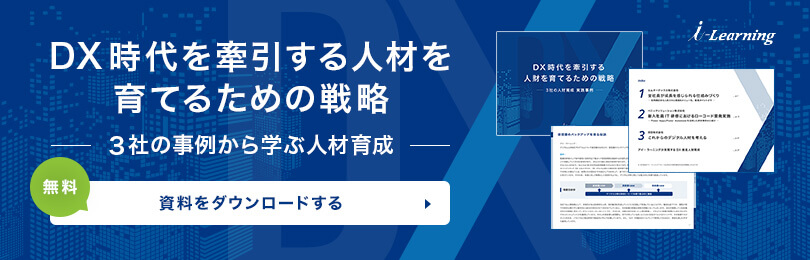ビーウィズ株式会社様
伊東 雅彦(右)
執行役員 CDO IT基盤部長
2000年8月の入社以来、コンタクトセンターのオペレーションを経て、現在はCDO(最高デジタル責任者)として、DXや生成AIを含むIT活用を推進するミッションを担う。サービス品質の向上を目指した、組織全体のDXや生成AI活用のボトムアップに取り組む。
羽生 智(左)
経営企画部 担当部長 ビジネスデザイン・サービスデザイン担当
BPO事業の枠組みを越え、クライアントの事業全体を支援する新たなサービス形態の企画・推進から社内外への戦略提案、他社との事業連携などの新しいビジネスモデルの構築を推進している。
古川 真澄(中央)
品質マネジメント部 部長
ビーウィズ最初の新卒採用世代として、コンタクトセンターのオペレーション業務からスタート。現在は、事業全体のサービス品質の維持・向上を担う品質マネジメントの一環として、人材育成全般の企画・運営に携わっている。
――はじめに、ビーウィズ株式会社の概要と事業内容について教えてください。
古川氏:当社は、2000年5月に三菱商事株式会社とソフトバンクグループの合弁事業会社として設立し、コールセンター運営を受託してきました。2012年より株式会社パソナグループの出資により、パソナグループと三菱商事の合弁事業会社となりましたが、2015年12月からはパソナグループ100%出資の完全子会社となり、2022年に東証一部に上場しました。
事業内容は、現在、コンタクトセンターとBPO事業に加えて、自社開発プロダクトの外販事業も行っています。おもな自社開発サービスとしてクラウド型PBX「Omnia LINK」、オンライン接客・契約システム「UnisonConnect」、AIエージェント「Tetory」、応対品質自動評価・教育プラットフォーム「Qua-cle」などがあります。
――今回実施された研修は具体的にどのような内容ですか?お三方の研修における役割やかかわり方についても教えてください。
古川氏:私の所属する品質マネジメント部は、元々、コンタクトセンター運営における管理者のスキル定義や教育、品質管理・改善を担当していましたが、2023年から正社員教育も担うことになりました。また、同時に社内でDX系の教育を強化することとなり、契約社員以上の全社員を対象としたDX教育を開始しました。その流れの中で、2024年度より一部の正社員を対象としたDX研修を企画・運営することとなったという経緯があります。具体的にはアイ・ラーニングのDX超入門(1日)、IT最新動向(1日)、デザイン思考ワークショップ(2日間)、VUCA時代の思考法(1日)、DX提言ワークショップ(2日間)を組み合わせて、5プログラムを計7日間で実施しました。
伊東氏:CDOである私の仕事の一つに、DXや新しいテクノロジーを使って、お客様に適切なサービスを提供できるよう全従業員に浸透させるというミッションがあります。今回実施したDXの研修は、社内では”DXデザイナー研修”と呼んでいるのですが、当社全体のレベルを向上させていくために必要な取り組みの一環です。また、今まで人事部が担当していた新入社員研修や、各部門の事業起点の人材育成も品質マネジメント部で行うことになりました。
羽生氏:私は経営企画でビジネスデザインを担当しているのですが、今はBPO事業の枠組みを越えてクライアントの事業全体を支援していく、という状況になってきています。お客様に提供するサービスやソリューションを企画するだけでなく、それを実現するための手法や考え方を社内外に発信する役割も担っています。DXデザイナー研修にもそうした立ち位置でかかわっています。
アイ・ラーニングを選んだ経緯と背景
――アイ・ラーニングとのお付き合いが始まったきっかけや時期について教えてください。アイ・ラーニングを選ばれた理由は何だったのでしょうか?

古川氏:アイ・ラーニングとのお付き合いは2024年2月頃からです。これまでの研修とは違うアプローチを模索していたところ、アイ・ラーニングのホームページが目に留まりました。
研修会社をいくつか比較したのですが、DX研修と謳っていてもIT知識に重点を置いているところが多いと感じていました。そのなかでアイ・ラーニングは、DXを手段として活用し、価値を生み出すための本質的な考え方に焦点を当てた講座内容であったことが、選んだ理由の一つです。また、カリキュラムが豊富なことはもちろん、デザイン思考をベースとしたプログラムが体系立っていてわかりやすいと感じました。
そして、最初の相談から当社の課題を高い解像度で理解してくださり、研修内容の提案も当社のニーズにフィットした点でした。また、アイ・ラーニング担当者の研修への熱意とレスポンスの早さも決め手ですね。
弊社としては、DXはあくまで手段であり、「お客様の課題に対して、どのようにDXを活かして価値を提供できるか」が重要だと考えています。そのため、そういった人材の育成につながるのかという視点からアイ・ラーニングの研修を選びました。
研修受講者の選抜と研修の実施
――受講者は選抜制で決められたと聞いています。研修を進めるうえで苦労された点などがあればお聞かせください。
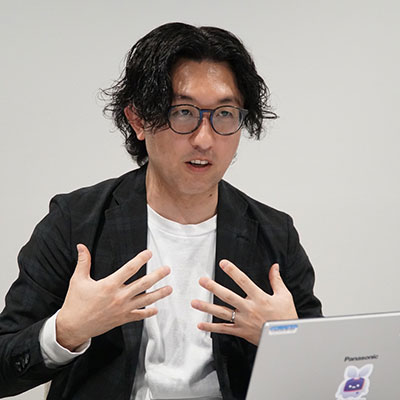
羽生氏:私を含めて伊東、古川の3人ともオペレーション出身なので、現場起点でどうビジネスを成長させるか、サービスの品質やレベルを高めるかという視点を強く持っています。今回の研修も、泥臭くリアルな発想でDXを牽引できる人材を育てようという切り口から、受講者の選定は希望者を募ったうえで選抜制を採用することにしました。
また、研修のゴールは個人のスキルアップではなく、組織や事業の成長につなげることです。そのため、ある程度の熱量やプレッシャーを持って参加してほしかったのです。
古川氏:今回の研修対象は、管理職以外の社員です。応募者が30人以上いたなかで、12名を選出しました。研修の趣旨を踏まえて、「お客様にどのような価値を提供できるか」「誰かに何かしてあげたい」という思いが特に強かった人を中心に選んでいます。
―選考には時間を要したのでしょうか。
伊東氏:選考自体は比較的スムーズでしたね。重視したのは視座の高さで、目の前の課題解決だけでなく、より広い視点や全社視点で物事を考えられる人をピックアップしました。選ばれた場合は、丸一日仕事を抜ける日もあるので、業務や部署内の調整ができないといけません。そういったハードルを乗り越えられる熱意や意欲が必要であるにもかかわらず、30人以上が応募してくれたのは非常にありがたかったです。
羽生氏:想定していたターゲット層から外れているにもかかわらず、どうしても参加したいという熱意ある応募者もいました。最終的には受講してもらうことになりましたが、その協議に少し時間がかかったくらいです。
古川氏:そうですね。ただ、受講したメンバーにこれから組織としてどのような役割を担わせていくかという点がまだ確立されていないので、その点は後の課題と考えています。研修で得た視点や思考を実際の業務でどう活かしてもらうか、組織全体のDX推進にどうつなげていけるかを考えていきたいです。
研修の効果・感想
――研修の感想などで印象的な言葉や、受講された方の研修効果を実感する場面はありましたか。
古川氏:研修終了後に受講者を集めて卒業式を行ったのですが、その場では「視野が広がった」「世の中のお客様の視点に立つことができた」といった声が多く聞かれました。やはり「お客様の視点に立つことができた」というコメントが印象的でした。
カスタマー視点の獲得や一つの事象に対する見方が広がるなど、受講者それぞれが異なる気付きを得られたことが今回の研修の意義だったと思います。何かができるようになったというより「スタート地点に立てた」ことが収穫ですね。ただ、スキル習得の研修ではないので、効果として表れるのは少し時間がかかるのではないかと考えています。
羽生氏:受講者のなかには、お客様の相談内容を持ち帰って「こう言っているけれど、多分こちらが問題だと思う」と相談してくるメンバーが出てきています。お客様の課題にマッチしそうな製品を当てはめて終わりではなく、本質的な課題解決をしよう、という変化が感じられました。まだ一部ですが、デザイン思考などを含む研修の効果で視座が変わってきたことが成果として見えています。
また、研修を受講した営業担当者が、本来の担当分野ではない案件について「DXデザイナー研修を受けたから対応したい」と上司に申し出たケースもありました。お客様の根本的な課題や目的に寄り添う必要がある案件に、積極的に取り組む姿勢が見られるようになっています。
今後の展望とアイ・ラーニングへの期待
――今後の人材育成への展望について教えてください。そのなかで、アイ・ラーニングにはどのようなことを期待しますか。

伊東氏:今後の展望としては、社員一人ひとりに新しいテクノロジーを活用して課題解決に取り組めるようになってほしいですね。現状では、クライアントの目的や意図まで深掘りできていないケースも多いので、お客様の真の目的をヒアリングし、最適なアウトプットを提案できるレベルまで引き上げたいと考えています。
羽生氏:事例や経験則だけでなく、未知の領域でも仮説を立ててお客様と対話できる会社になりたいと思っています。現在はお客様の要望でBPOをお受けする関係が中心ですが、提示された課題感を上回る視座で弊社が提案する、という形が理想です。お客様の一歩先をリードする伴走型のパートナーになることを目指しています。
そのためには、社員一人ひとりが仮説を立てる力を身に付け、構想から実現、改善まで一気通貫で対応できるよう、組織全体の標準レベルを引き上げる必要があります。ときには、妄想のような飛躍ある仮説も立ててほしいですね。
古川氏:アイ・ラーニングには、今後も研修を考える際の相談相手になってもらいたいです。DX研修はどのようなコンテンツが最適か判断に迷うこともあるため、研修の専門家からのアドバイスは貴重ですから。今回は選抜メンバーで実施しましたが、2025年度は同様のプログラムで正社員層を対象として展開する予定です。
“失敗しない”思考を覆す、DXの本質的イメージが伝わる研修
――最後に、DX人材の育成に取り組まれている企業に向けて、メッセージをお願いします。
伊東氏:アイ・ラーニングの講師の方々はどなたも面白く、DXに対する考え方を土台から変えさせられました。
そういった点で、DXに対して思い込みがあり、失敗しない仕事のやり方がすでに固まっているような企業は研修を受けたほうが良いかもしれません。蓄積した知見やノウハウで仕事を回すことが中心になると、社員一人ひとりは外を見なくても仕事ができてしまいます。そういった業界の枠にはまっている企業ほど、アイ・ラーニングの研修を受けることで、DXの本質的な意味や目的を理解し、表面的な取り組みを脱却した真の価値創造にもつながると思います。
羽生氏:「言われたことをやる文化」によって自律的な変革が進まない企業や、従来のやり方に固執して変化することへの抵抗がある企業には非常に効果的だと思います。また、現場の社員だけでなく、役員も率先して受けることで組織全体の改革も進みやすくなります。
DXに対して「どう変わるかが想像できない」場合、具体的なイメージを提供できる研修としてアイ・ラーニングの研修は大きな価値があるのではないでしょうか。

アイ・ラーニングコラム編集部
育成に関するお悩みや課題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。