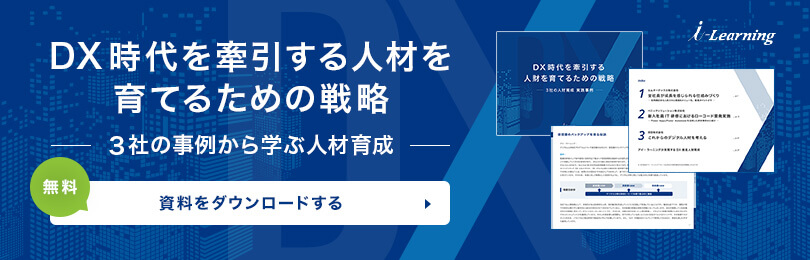アセンテック株式会社様
左から第一システムサービス部 磯田 大智、第一営業部 小島 千奈、人事総務部 若松 未来
今回は、アイ・ラーニングの新入社員向け「インフラエンジニア育成コース」を導入されているアセンテック株式会社様にインタビューを行いました。人事総務部の小山田様・長嶋様・若松様からは研修担当者としてのご意見を、受講者の磯田様と小島様からは研修を受講した率直なご感想を伺いました。
――まずはアセンテックについてお聞かせください。
小山田氏:
アセンテック株式会社は、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びシステムインテグレーションやコンサルティングサービスの提供を行っています。企業向けの比較的高度なソリューションであるため、お客様に最適な提案ができるスキルの高い営業社員や、お客様の要望に沿ってシステム構築のできるデリバリー能力の高いエンジニアなど、将来大きく成長する社員を育てることが大事と考えています。
研修の目的・研修に求めること
――研修の目的や、貴社が新入社員研修に求めることについてお聞かせください。
長嶋氏:新入社員の方々には、アイ・ラーニングの約2ヶ月間の研修を通じて基礎知識をしっかりと習得してもらい、その後の配属先で、営業職・SE職いずれでも活躍できる土台を築くことを目的としています。
学生から社会人へと移行する新入社員は、知識も経験も乏しい状態です。アイ・ラーニングのインフラエンジニア育成研修は、ビジネスマナーなどの社会人基礎と、ITの基礎が、幅広く網羅されています。研修内容が直ちに実務に結びつかなくとも、そこで得たIT基礎が1年後、2年後に役立ったという声も聞いています。特定のITスキルに偏らず、バランスの取れたITのオールラウンダーを育成する上で、優れた研修内容だと評価しています。
この研修は、2018年から導入しています。導入当初、もし研修効果が本人や人事担当者から見て実感できなければ、継続は難しかったでしょう。しかし、この研修を基礎として多くの若手社員が活躍してくれています。研修で学んだことが自信に繋がり、結果として若手の離職率が非常に低いという実績にも表れています。これは、研修での学びが土台となり、配属後の部署での指導やメンター制度などの育成との組み合わせによる、好循環の証だと考えています。
小山田氏:当社では社員が仕事で活躍し、ご自身は達成感と自信を得て、周りの方々から評価されて、さらに意欲を高めて、学び成長するという、好循環を生み出すことを目指しています。入社後は、数日のオリエンテーションを経て、アイ・ラーニングのエンジニア育成コースで、ビジネス基礎とITの基礎を学んでもらいます。研修終了後すぐに現場配属とはせず、人事部で約1週間、「仕事への向き合い方」や「周囲との良好な関係構築のための要素」といった事柄を改めて確認した上で、現場へ送り出しています。
配属後はメンターをアサインして、特にハイブリッドワーク環境下でも相談しやすい体制を整えています。OJTに励んでいただき、段階を踏んで現場に慣れてもらい、1年後には次の新入社員を迎えるというサイクルの中で、緊張感を持ちながら成長していってほしいと考えています。
研修の導入経緯
――2018年から導入されたと伺いましたが、それ以前は研修をどのように行っていたのでしょうか。
長嶋氏:以前は新入社員を毎年継続的に採用するという体制自体が整っておらず、採用や教育に関する取り組みはほとんどできていませんでした。社内ルールを最低限説明する程度で、現在と比較すると十分な教育体制ではありませんでした。
――導入当初は、どのような点を重視して研修プログラムを設計されたのでしょうか。
小山田氏:当初から現在のような育成計画があったわけではありません。新卒採用を開始して、育成の必要性を感じた際に、以前から知っていたアイ・ラーニングの研修を導入しました。その後、試行錯誤しながら改善を重ねている状況です。
研修の効果・実績
――具体的にどのような点で研修の効果を実感されていますか。
長嶋氏:効果としては、入社数年の若手社員が比較的早期にプロジェクトに参加し、顧客からも評価を得て活躍している事例が見られる点です。これはやはり研修を修了したという実感と、勉強し続けるという習慣が身についた結果ではないかと感じています。研修当初は不安を抱えていた社員も、研修での努力が自信となり、実際の業務として数値目標達成やプロジェクト完遂などに繋がっています。若手社員が目標を一つずつクリアし、現場で活躍している姿を間近で見ることで、研修の効果を感じます。
小山田氏:採用時には素養のある人材を採用するよう心がけています。素養のある方が、前向きに学び続ければ、立派な社会人、優秀なビジネスパーソンになれると考えています。
長嶋氏:当社は、毎年ストレスフリーカンパニーに表彰されるなど、会社の雰囲気の良さも、社員がのびのびと活躍できる一因となっていると考えています。
若松氏:入社後は、人事で数日のオリエンテーション後に、研修に入っていくのですが、その過程で新入社員の方々の成長を感じることがあります。例えば最初は控えめであまり発言のなかった新入社員も自ら積極的に発言するようになっていて、これも研修の成果だと感じます。今後の活躍に期待をしています。
――研修期間中、貴社では受講者に対してどのようなフォローを行っていますか。また、苦労された点などはありますか。
小山田氏:苦労というよりは、心がけていることがあります。まず、応募段階から入社後の学習意欲を喚起しています。「入社後はこれまでにないほど勉強してもらう」と伝え、学習への心構えを促しています。理解度テストの実施や、社会人として勉強する習慣の重要性を強調し、ある程度のプレッシャーを与えた上で研修に参加してもらっています。
長嶋氏:研修の中で受講者は日報を作成するのですが、講師やクラスマネージャーの方々が的確で励みになるコメントを書いてくださっていることが印象的です。受講者にとっては、人事担当者も見ている状況で本音を書きにくい側面もあるかと思いますが、講師が本人の状況を的確に捉え、時には指摘し、時には励ます、そのやり取りが大変ありがたいと感じています。
小山田氏:日報は短い文章であっても、受講者が何を考え、何に気づき、どこで躓いているのかがよく分かります。オンラインでの週1回のミーティングや、必要に応じた個別面談を通じて、状況把握とフォローを行っています。私たち人事担当者も、研修内容や講師のコメントだけでなく、受講者を継続的に見守ることが重要だと考えています。
――研修終了後、時間が経過してから現れる効果や、印象に残っているエピソードなどはありますか。
小山田氏:研修を通じて「勉強することが当たり前」という姿勢が身につくことを期待しています。ある社員は研修後も学習を継続し、当社の仕事で求められているわけではないのですが、IT全般の基礎力強化の意味合いで、情報技術者試験を受験する社員もいます。また入社以来、毎日欠かさず日報を書き続けている社員もいます。これは素晴らしいことで、このような社員は大きく成長する可能性が高いと感じます。
長嶋氏:研修期間中は自信なさそうに見えた社員が、現場配属後に生き生きと活躍している姿を見ると、研修での頑張りが現場での活躍に繋がっているのだと感じます。効果の表れ方は人それぞれですが、何らかの形で研修が良い影響を与えていると感じています。研修での経験が自信となり、困難を乗り越える力になっているのではないかと推察します。
小山田氏:営業部門のように、改めて勉強時間を確保することが難しい場合でも、研修で基礎知識を学んだ経験は、新しい技術を理解するための土台となっていると思います。
アイ・ラーニングのインフラエンジニア育成研修のように、IT全般を幅広く学ばせるカリキュラムは貴重だと考えています。例えば、当社の現在の主力製品では直接的な関連性は低いデータベースの知識であっても、データの動きからセキュリティ対策を講じるソリューションなど、新しい技術を理解する上で役立つ可能性があります。
アイ・ラーニングへの期待
――今後、アイ・ラーニングにはどのような支援を期待しますか。
長嶋氏:研修内では他社の方とグループワークをする機会があり、受講者にとって良い刺激となっています。そのため、グループワークの人数は減らさず、他社の方との交流をより深められることを期待しています。
小山田氏:新人研修を40数日間のコースとしてではなく、1年後・3年後のフォローアップ研修もあらかじめ含まれているとありがたいと感じます。
若松氏:担当させていただくようになってからそれほど時間が経っておらず、分からないことも多いため、アイ・ラーニングには運営も含めたトータル的なサポートを期待しています。

――最後に、同じように新入社員研修を検討されている企業に向けて、メッセージをお願いします。
小山田氏:アイ・ラーニングのインフラエンジニア育成コースは、当社のようにビジネスパーソンとしての基礎とIT基礎を幅広く学ばせたい企業にとって、適していると思います。また、講師の方々が受講者一人ひとりの日報に的確なコメントをくださるなどのフォロー体制は素晴らしいと思います。
長嶋氏:研修制度の充実は、採用活動においても応募者からの関心が高い項目です。特にIT未経験者にとって、入社後の学習に対する不安は大きいですが、しっかりとした研修を通じて自信をつけることが、結果的に離職率の低下に大きく貢献していると考えています。
長嶋氏:毎年継続して研修を実施することで、先輩社員が後輩の面倒を見るという良い循環も生まれており、これも大切な成果だと考えています。
実際に受講された方の声

磯田 大智(左)
所属:第一システムサービス部 SE
2024年にアセンテックに入社。仮想デスクトップの環境設計や環境構築などの業務を担当。実際に顧客の現場へ赴き、システムの構築や試験などを行う。
小島 千奈(右)
所属:第一営業部 営業
2022年にアセンテックに入社。仮想デスクトップおよびセキュリティ製品を中心に、ハードウェア、ソフトウェア、および自社SEの技術力を組み合わせたソリューションを提案。
研修を実際に受講してみて
――ここからは実際に研修を受講した磯田様、小島様にもお話をお聞きします。お二方は研修に対して不安などはありましたか。
磯田氏:私は経済学部出身ということもあり、ITの知識がほぼゼロの状態で入社したので、「そもそも研修内容を理解できるのか」という不安がありました。
小島氏:私も文系で、理系の同期と同じ研修を受けることにプレッシャーを感じていました。工学部出身で最初からSE志望の同期もいたので、「理系の人とはそもそもスタートラインが違うのではないか」と不安を感じていました。
――研修中、その不安は解消されましたか。
小島氏:研修は他社も含めた合同クラス形式で進んでいくのですが、最初は工学系の学部出身者との知識ベースの違いは感じたものの、不明点をグループのメンバーが知識を共有し助けてくれたこと、講師陣も参加者のレベルを理解した上で進行してくださったことで、焦りや過度な不安を感じることはなくなりました。研修を通じて、当初抱いていた不安は、徐々に払拭されていきました。
研修の内容・感想
――印象に残っている研修内容やプログラムはありますか。

磯田氏:最も印象に残っているのは、研修後半に行われた総合演習です。グループで計画立案からシステム構築、最終発表までを一貫して行うもので、配属前の疑似的な業務体験として、仕事の進め方を学ぶ良い機会になったと感じています。約2ヶ月間の研修で学んだ技術要素のほぼすべてを活用するため、知識の振り返りにもなりました。
小島氏:私は当初IT知識が少なかったため、研修初期の「情報システム基礎」のような基礎知識に関する内容は、通常業務で改めて教わる機会がないことから、研修のタイミングで学べて良かったと感じています。また、AWS(Amazon Web Services)を用いたクラウド環境の構築演習も印象に残っています。実際に手を動かして構築を経験したことで、今後の業務におけるイメージが掴みやすくなりました。
――グループワークやワークショップについてはどうでしたか。
磯田氏:研修前半は初対面の参加者も多く、グループワークの進行に苦労する場面がありました。しかし、後半になると、メモ担当、タイムキーパーといった役割分担を明確にしたり、発表者を順番に担当したりすることで、効率的に進められるようになりました。
小島氏:研修を通じて、オンライン会議の進め方などを習得できました。特に総合演習は、プロジェクトマネジメントの疑似体験として有意義であったと感じています。WBS(Work Breakdown Structure)の作成から、役割分担、進捗管理まで、実際のプロジェクトの流れを学ぶことができました。計画通りに進まないといったリアルな経験も含め、SEの業務やプロジェクトの動き方を理解することができました。
業務への活用について
――研修で学んだことが現在の業務に活かせていると感じますか。

小島氏:研修で学んだプロジェクトの流れやその関連知識は、現在の営業活動においても、例えば、システム構成図、提案書、納品ドキュメントなどを作成・理解する上で役立っています。
磯田氏:最近、実際の業務において、「RAID(Redundant Arrays of Independent Disks)」に関する知識が必要となったのですが、研修で学んでいなければまったく理解できなかったであろう内容で、研修の知識が役立ったと実感しました。
小島氏:社会人としての基本的な、名刺交換、メール作成、報告書の書き方といったマナーや、プレゼンテーション、コミュニケーションスキルといった、会社に入れば当然身についているべきとされる基礎的なスキルを研修で学べたことは非常に有益でした。学生から社会人への移行期間として、心構えや生活リズムを整えるという点でも良かったと感じています。
――配属時の心境にも影響はありましたか。
小島氏:一つ一つの課題をクリアしていく中で自信がつき、配属当初の不安が軽減されました。研修で得た知識やスキルをどう活かすかという新たな不安はありましたが、SEと共に研修を乗り越えたという達成感は大きかったです。
磯田氏:2ヶ月間の研修期間があったことで、入社直後に配属される場合と比較し、技術面での不安は確実に軽減されました。もちろん「これから本格的に仕事が始まる」という責任感から、技術的な不安というよりプロフェッショナルとしての仕事が始まることへのプレッシャーはありました。
研修の価値について
――お二人が考える研修の価値とは何だと思いますか。
磯田氏:約2ヶ月半のビジネス基礎を含めた研修は、社会人として、またSEとして働く上での最も基礎となる部分を学ぶ貴重な機会でした。技術面だけでなく、作業前の「定量化」の習慣や、不明点を放置せず早期に解決する姿勢が身についたことは大きな収穫です。特に後者は、研修中に不明点を放置した結果、後の進行に支障が出た実体験から学んだ教訓です。
小島氏:社会人になりたての不安な時期に、同じ状況にある、多くの社内外の同期と交流しながら学べたことは、励みになると同時に非常に価値あるものでした。文系出身で営業配属という立場であっても、日々の課題をクリアしていく経験が自信に繋がり、配属前の不安を和らげる上で研修全体が大きな意味を持ちました。
クラスマネージャーの役割について
――講師とは別に勉強時間以外もフォローを行うCM(クラスマネージャー)はどのような存在でしたか?
小島氏:研修の最後に配属後のキャリアプランなどを記入する目標シートを作成するのですが、営業職としてのキャリアパスについてクラスマネージャーに相談し、納得のいく目標設定ができました。また、日々の細かな疑問や不安を相談できる存在がいることは、精神的な支えにもなりました。
磯田氏:技術研修期間中、研修開始前と終了前の各30分にクラスマネージャーとの時間が毎日設けられていたのですが、ビジネスマナーについて継続的に指導を受けられたことが良かったと感じています。最初のマナー研修だけでは学びきれない部分を繰り返し復習し、メール作成の添削など、実践的な指導もしていただき、マナーが深く身についたと感じています。日報の書き方についてもアドバイスをいただいたことで、文章作成能力の向上に繋がりました。
インタビューを終えて
人材不足が企業の課題となる中、新入社員の育成と定着は重大なテーマです。インタビューでも「研修前に不安はあった」とコメントいただきましたが、研修を通じて不安を乗り越えていく過程が印象的でした。社外も含むグループメンバーやクラスマネージャーに支えられながら、単なる知識習得にとどまらない実践的な研修を通じ、社会人としての心構えや自信を育むことができたのだと感じました。
アイ・ラーニングコラム編集部
育成に関するお悩みや課題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。